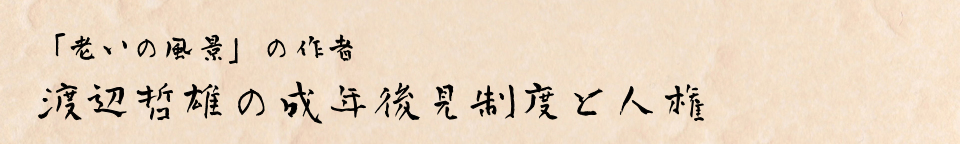- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 福祉サービスの死角(2)
福祉サービスの死角(2)
その日、吉島敬三は、地域包括支援センターの山本社会福祉士に同行されて、生まれて初めて家庭裁判所の建物に足を踏み入れた。山本の支援を得て、保佐の申立てに必要な書類一式は、診断書を含めて既に提出が済んでいる。本日は事務官との面接が予定されていた。山本からは、聴かれたことに落ち着いて答えればいいと言われていたが、独特の静寂に包まれた家庭裁判所で、紺のスーツ姿の事務官と向き合うと、気の小さい敬三は訳もなく緊張した。
「初めまして、私、事務官の古田と申します。保佐開始の申立てを受理していますので、そのことについて直接ご本人に色々お尋ねいたしますね」
事務官は申立ての書類を丹念に確認しながら、
「まずお名前は何とおっしゃいますか?」
「吉島敬三です」
敬三の声は心なしか震えている。
「楽にして下さいね、吉島さん。年齢はおいくつですか?」
「七十…あ、八十になったかな?」
敬三は年齢が言えない自分に改めて驚いている。
事務官は手元で何やら記録をしているが、それが自分の態度や反応の正確さであるかと思うと、敬三はさらに緊張した。
「倒れて意識がなかったそうですが、元気になられて何よりです。発見が早かったおかげですね」
事務官は笑顔を作り、しばらくは入院中の様子や、生活歴を質問して、敬三の生活の背景や状況を把握していたが、やがてわずかに背筋を伸ばし、
「申立書によると、あなたには身寄りがなくて、保佐人の選任は裁判所に任せたいというご意向のようですので、弁護士か司法書士が選ばれると思いますが、代理行為目録の通り、財産管理を保佐人に任せるということでよろしかったですか?」
言葉が難しくてよく分からないが、分からないからこそ、敬三にはうなずくしかなかった。
「では、通帳や印鑑は保佐人に預けて、月々必要な現金を渡してもらうことに致しましょうね。ご自分で持っているよりはずっと安全ですし、保佐人は裁判所がきちんと監督しますのでご心配は要りません。それからうっかり吉島さんが不必要な物を高い値段で買ってしまったり、ローンを組んでしまったときは、保佐人には契約を取消しておカネを取り戻す権限が与えられますからご安心下さいね」
「あ、はい」
敬三の表情はぼんやりしている。
「あと、代理行為目録によると、将来入院が必要になったり、福祉サービスを利用するときなどは、吉島さんに代わって保佐人に契約をしてもらうということでよろしいですね?」
「はあ…お願いします」
事務官は一時間余りかけて丁寧に敬三の意思確認を行った。質問には卒なく答えているように見えるが、端から崩れ落ちる吊り橋のように、敬三の記憶は失われて行く。
「それでは本日の結果を裁判官に報告して保佐人が決まり、二週間の告知期間中に異議の申立がなければ確定しますので、しばらくお待ちください」
終