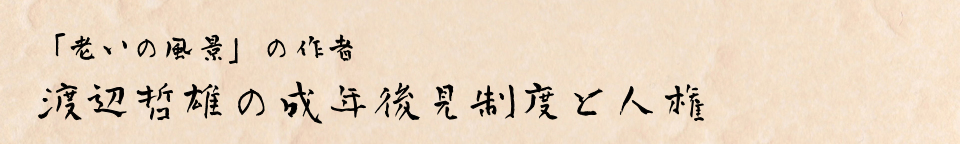- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 福祉サービスの死角(6)
福祉サービスの死角(6)
吉島敬三に対するホームヘルプサービスが始まった。
訪問介護だけで組み立てられた不自然なプランも、本人の意向だと説明すると、板橋保佐人はすんなりと了解した。
「例えば通院の帰りにご本人が一緒にお寿司を食べたいとおっしゃったような場合には、ヘルパーがお付き合いして構いませんか?それともご本人の近くの席で待機すべきですか?」
「近くで待機されていたら落ち着かないでしょう。ご本人が一緒に食べることを望んでいらして、二人分の費用がご本人の負担になることをご承知であれば、構わないと思いますよ」
「私どもは一緒にスーパーで食材のお買いものをして、三度三度調理して差し上げるのが健康にもいいし、生活に変化も出ると思うのですか、ご本人がどうしても外でお食事をしたいとおっしゃられる時は、どんなふうにお断りすればいいでしょう」
「いえ、成年後見制度は、浪費はいけませんが、できるだけご本人の意思を叶える方向で支援する制度ですから、そういう場合はご希望を叶えてあげて下さい」
「費用は大丈夫なのですか?」
「身寄りのない吉島さんは、潤沢な預貯金を持っていらっしゃいますが、財産を残す当てがありません。結局、国庫に入るだけですから、八十二歳という年齢を考えても、介護保険の枠にこだわらず、お元気なうちに有意義な人生を経験させてあげて下さい」
「分かりました。その方針でケアに臨みます」
前田ケアマネジャーとの間にこんな合意を交わした板橋は、保佐人の代理権を用いて、訪問介護事業所としての『楽福』と契約し、費用の口座引き落しのための預貯金口座振替依頼書に署名捺印したときは、それがどんな結果をもたらすのか、全く想像が及んではいなかった。
吉島敬三は自動車の部品製造工場の工員として、若い頃から指示されるままに黙々と作業に従事して生きて来たのだろう。認知症になって判断能力が衰えても、人に異を唱えない従順さは類を見なかった。
「吉島さん、昨日、うなぎが食べたいとおっしゃっていたので、お昼を予約しておきましたが、よろしかったですか?」
と言えば、素直にうなずいて、ヘルパーの菊池も一緒にうなぎを食べた。
「吉島さん、一人の夕食は淋しいから、たまにはすき焼き鍋を囲んで、お酒も飲んでみたいとおっしゃっていたでしょう?今夜はちょっと高級なお店に二人でお付き合い致しますね」
と言えば、嬉しそうに同行して、前田も菊池も一緒に松阪牛を味わった。
代金は、その間のヘルパー派遣の費用も加えて、板橋が管理している本人の口座から引き落とされた。
「吉島さんがメロンを食べたいとおっしゃっていたので、買って来ましたよ」
高級なマスクメロンも、敬三が一切れ食べた残りは、菊池が持ち帰って前田と半分ずつに分けた。
「最近コツが呑み込めたわ。吉島さんがおっしゃったからと前置きすると、記憶のない吉島さんはあいまいにうなずいて、結局本人の意向になるわ」
「そのことはちゃんと記録に残してね。後日私たちの身を守る」
前田と菊池は次第に大胆になって行く。
終