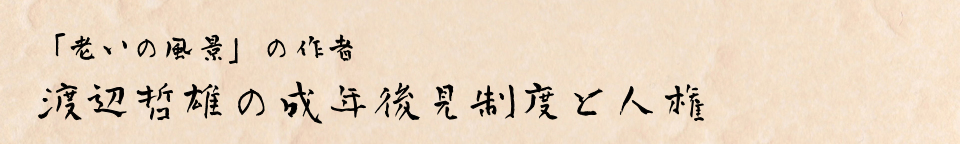- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 福祉サービスの死角(10)
福祉サービスの死角(10)
「法事ねえ…」
と前田ケアマネジャーは首を傾げた。
「吉島さんには身寄りがないのよ。ヘルパーのあなたがいるにせよ、認知症のお年寄りが一人きりで法事ったって…」
「うちの事業所全員でお兄さんの冥福を祈って差し上げたらどうでしょう。忘年会を兼ねて」
前田はようやく菊池の目的が理解できた。目的が理解できると前田自身がその計画に夢中になった。うまく運べば、登録ヘルパー六人の忘年会が負担なしに実現できる。
「僧侶は?」
「ご近所が菩提寺をご存知でしたので、七回忌の法要のお布施の相場も聞いておきました」
「いくら要るものなの?」
「五万円もあれば…」
「あら、思ったよりリーズナブルなのね。ということは、お斎って言うの?法要の後の会食を、飲み物を別に一人、八千円と見積もって…」
前田は電卓を叩き、
「全体で十五万円もあればお釣りが来るのよね」
二人は顔を見合わせた。
相続人のいない敬三が亡くなれば、財産は国庫に帰属する。それよりはヘルパーたちと賑やかに料理を楽しんだ方が本人にとって意義がある。敬三に残された人生は、せいぜいあと十年なのである。
「ご本人の方は大丈夫?」
「もちろんですよ。私、吉島さんほど穏やかな人を知りません。法事をしましょうと言えば頷かれるし、法事はやめましょうと言っても頷かれます。そして頷いたことを覚えておられません。外の食事や楽しい集まりがお好きですから、本当はうちの事業所にもデイサービスがあればいいのですがね」
「あら、デイじゃ収益にならないじゃない」
「確かに」
二人が弾けるように笑ってから二十日後に、吉島敬三の弟の七回忌が営まれた。
住職が来て仏壇の前で読経を始め、敬三は、前田ケアマネジャーと菊池ヘルパーの間で行儀よく座って手を合わせている。
「さ、吉島さん、お焼香ですよ」
菊池に手を添えられて敬三が焼香を済ませると、手配してあったタクシーが玄関に来た。
「本日はどうも有難うございました。お兄さんの法要をしたいという吉島さんの願いが叶えられて本当によかったです」
ね?と菊池が微笑むと、敬三は恐縮したように頭を下げた。
「ご一緒にお斎をとも思ったのですが、何しろ吉島さんには身寄りがないので、お食事代を同封しておきました」
七万円の入った封筒を渡して住職のタクシーを見送った頃、もう一台のタクシーが来た。
「さ、吉島さん、今日は法事を兼ねた忘年会ですよ。吉島さんのためにうちのヘルパーたちも参加します。楽しんで下さいね」
三人を乗せたタクシーは、この辺りでは名の通った駅前の料亭『萩乃家』に向かった。
敬三は菊池の隣で、車窓を流れ去る夕暮れの街並みを無感動な表情で眺めている。
終