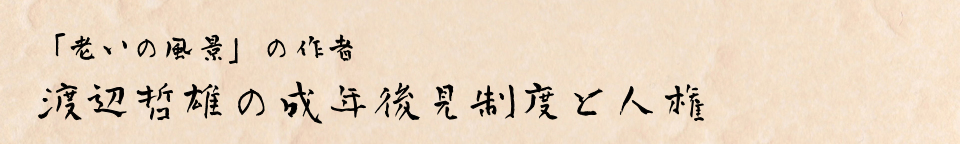- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 福祉サービスの死角(11)
福祉サービスの死角(11)
年が明けて、ひと月が経った。板橋法律事務所では、訪問介護事業所『楽福』から郵送された吉島敬三の十二月分のサービス費用と、通帳から引き落とされた金額を、事務の田崎敦子が怪訝な顔をして見比べていた。
「どうした?金額が合わないのか?」
板橋弁護士が、淹れたてのコーヒーを立ったまま一口啜って背後から声をかけた。
「いいえ、金額は合うんですが、今月はいつもより十五万円出費が多いんです」
「十五万円もの出費であれば事前に保佐人に相談が欲しかったなあ」
費目は分かっているんだろうと言う板橋に、
「お兄さんの七回忌の法要費用と書いてあるんですけどね、吉島さんって身寄りがありませんよね?」
「坊さんへの支払いを事業所が立て替えたってことか…しかし、十五万円が不適切であったとしても、保佐人が法要やお布施を取消すって訳にはいかないだろう」
「それはそうですが、そもそもお兄さんの七回忌なんて、認知症の吉島さんが思いつくでしょうか」
「誰の法事をいつやるかは、ちゃんと寺に記録がしてあって、忘れている遺族に住職の方から促すものらしいよ。何しろ葬式や法要が寺の収入源だからね」
「事業所に領収書は取ってありますかねえ…」
「お布施に領収書かあ…一般的には取らないかも知れないな」
「とにかく私、『楽福』のやり方には普段から何となく疑問を感じていたんです。新しい年になったことですし、今回の法要の件をきっかけに、吉島さんご本人にも伺って、ちょっと調べてみたいと思います」
板橋の許可を取った敦子は、まずは吉島敬三の家を訪ねた。
「ごめん下さい、吉島さん」
ヘルプの時間を外して出かけると、敬三は一人で家にいた。
家の中はいつものように掃除が行き届いていて、窓際に洗濯物が干してある。一見して、いい加減なヘルプをしているという印象はない。
「私、いつもお小遣いをお届けする板橋法律事務所の田崎です」
「あ、はい。お世話になります」
敬三は腰が低い。
「板橋弁護士が、よろしくと言っていました」
「それはどうも…」
「吉島さんのヘルパーの菊池という女性、覚えていますか?」
「はい。よく覚えています」
「女性にしては背が高くて、黒縁の眼鏡がちょっと怖い感じですが、ああ見えてやさしい人ですからね」
「それはもう親切にしてもらっています」
「ところで吉島さん、ヘルパーの菊池いう男性はご存知ですか?毎日吉島さんのお世話をしてくれると思いますが…」
「はい、それはもうお世話になっています」
にこにこと頭を下げる敬三の様子に敦子は驚いた。敬三は何も認識していない。ただ、長年の生活経験で身に着けた会話のパターンで、習慣のように相手に合わせているに過ぎない。
こうなると敬三の意思を尊重して実施されているはずのヘルプの内容も、日誌通りとは限らない。
終