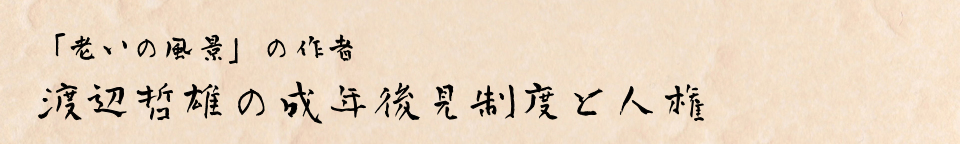- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 誤算Ⅰ
誤算Ⅰ
梶浦法律事務所を訪ねて来た樋口敦子と名乗る女性は、
「私…母をあんなひどい目に遭わせたグループホームをどうしても許せないのです」
思い詰めた様子で経緯を話し始めた。
敦子の母である樋口美佐子は、突然の心不全で夫を亡くしてからというもの、随分長い間うつ状態が続いていたが、やがて深夜に目を覚まして大声を出したり、ハンガーに掛けてある衣類に話しかけたりするようになった。
「キッチンのテーブルに向かい合う二つの椅子を見て、可愛い子どもが二人いると大騒ぎをするものですから、これはおかしいと思って、近くの病院で診てもらうと、レビー小体型認知症と診断されました」
症状は気まぐれに進行したが、主治医の説明通り、次第に手が震え、表情が乏しくなり、一度立ち止まると足がなかなか前に出なくなって、排泄の失敗が増えた。
「母は私に仕事を辞めて一緒にいて欲しいと言いました。そういうときの母は別人のようにしっかりしていて、お前が会社を辞めても遺族年金と借家収入で生活は何とかなる。貯えには手を付けなくて済む…と、金額まできっちり計算するのです」
敦子は母親を放ってもおけず、定年前に建設会社の事務を辞めて家事と介護に専念した。広島に嫁いだ妹と違って、こういうとき独身の敦子は身軽だった。
「…二年間は何とか頑張りました」
前かがみに突進して家具にぶつかったり、こんな知らない家にはいられないと夜中に出て行こうとする美佐子を、敦子は体当たりで介護した。
「要介護認定を受けてヘルパーを利用してみましたが、買い物や調理をしてもらうのがせいぜいで、焼け石に水でした」
深夜に起きだして、居もしない来客にお茶を淹れてもてなしたり、壁の汚れを指差してネズミがいると大騒ぎをする美佐子の行動に敦子はすっかり疲れ果てた。
「お前がいつまでも結婚しないのを気に病んでお父さんは心臓を悪くしたんだ!と怒鳴った母が、私の泣き顔を覗き込んで、どなたか知りませんがだいじょうぶですか?と他人の目で聞いたとき、もう限界だと思いました」
敦子はケアマネジャーに相談して美佐子をウェルフェアという大手のグループホームに入居させた。
「そこでひどい目に遭ったのですね?」
梶浦弁護士はすっかり敦子に同情していた。梶浦にもアルツハイマー型認知症の母親がいるが、弁護士の妻と一緒に法律事務所を開設した梶浦には家庭で介護するゆとりはなく、早々に有料の老人施設に預けて、最近では面会の足も遠のいている。
「私、毎週グループホームに面会に行くつもりでした」
「つもり…と言いますと?」
「入居して三日目に施設長から電話があって、母がホームの生活に慣れるまで毎日通って欲しいと言われたのです」
「毎日…ですか?それじゃ預けた意味がないですね?」
「一緒に泊まれとまでは言われませんでしたから、それだけでも随分助かりました」
「夜も泊まったんじゃ職員と変わりませんからね」
「でも、今となっては泊まった方が良かったと思っています」
終