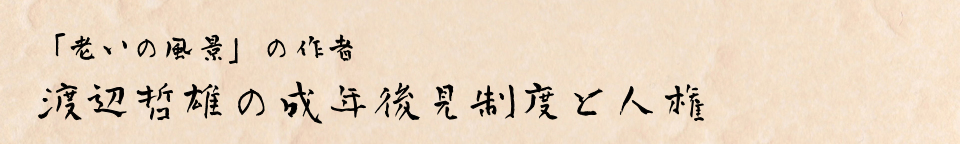- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 誤算Ⅲ
誤算Ⅲ
「骨折のお話しの前に、痣の原因は分かったのですか?」
虐待の提訴が相談目的であることを考えると、弁護士としてはまずはそこを押さえておきたい。
「それが、約束通り母は次の朝、提携医院に受診したようですが、痣からは原因は特定できないとの回答でした」
「提携医院の立場はどうしても施設側になりますからね、そういう結果だろうと思いました。それじゃ、お母さまが骨折されたときの様子は詳しく分かりますか?」
梶浦の脳裏には、鎖骨と大腿骨を添え木で固定された痛々しい高齢者の姿が浮かんでいる。
「二度とも深夜の出来事で、ドスンという鈍い音に驚いて職員がドアを開けたら、母が居室で転倒していたと言うのですが、翌朝、連絡を受けて同行した整形外科のお医者さんから気になることを聞いたのです」
「気になること?」
「ええ、年配のお医者さんでしたが、鎖骨のレントゲンに目を近づけて、転んでこんなふうに折れるかなあ…と首を傾げるのを私、確かに聞きました」
「それは大事な情報です。その医師と骨折を発見した職員からは、改めてお話しを伺うことになるでしょう…で、お母さまは入院されたのですか?」
「私もなぜ救急車を呼ばなかったのかと聞いたのですが、グループホームは夜間、職員が一人ですから、脳出血や窒息や激しい痛みを伴うような場合だと別の職員を呼んで救急搬送もあるけれど、転倒の場合、通常は翌朝の診察になるそうです。それに認知症は、自分が骨折していることさえ忘れてしまいます。病棟で点滴を抜かれたり大声を上げたりされるのは困るので、病院としても極力入院は避けるようです」
「なるほど…」
梶浦の頭の中で、骨折した高齢者の顔が自分の母親の顔になる。それを払拭するように姿勢を正し、
「事情はよく分かりました…で、お母さまは今もグループホームに?」
「いえ、母をあんなところに置いておけません。ケアマネジャーさんにお願いして、特別養護老人ホームに移しました」
「元気にしていらっしゃるのですか?」
「大腿骨の骨折で動けないでいるうちに、レビーの症状が進んだのでしょう、終日おむつをしてベッドの上でぼんやりしています。もう私のことも…」
と敦子は言葉を詰まらせて、
「分からないみたいです」
声を震わせた。
「もとはと言えばあんなグループホームに入れた私が悪いのですが、素人のような若い介護職員に殴られて、骨を折られて…ぼろぼろになった母は可哀そうです。私はウェルフェアが許せません。法廷できちんと責任を追及したいのです」
梶浦は事務員にお茶を替えさせて敦子の興奮を鎮め、
「訴訟するにしても、お母さまは認知症で訴訟能力がありません。弁護士と代理人契約を結ぶ能力もありません。まずは家庭裁判所に後見人を選任する申立てを致しましょう」
「後見人?」
敦子には何のことやら分からない。
終