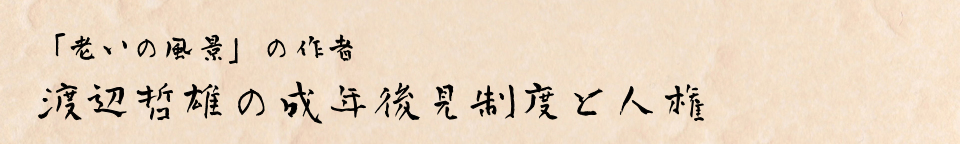- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 成年後見物語2
成年後見物語2
コップ酒を二つ空けたところで電話が鳴って、隆二は慌てて政子に目くばせをした。
「あ、はい、いえ、主人はあいにく留守をしていまして、はい、いつになるかはちょっと、はい、申し訳ありません」
政子が応対している間に、今度は玄関のチャイムが鳴った。
「ち、誰だ、こんな時間に」
うっかりドアを開けた隆二は、その場に棒立ちになった。
「居留守は困りますねえ、倉内さん」
黒いスーツの痩せた男が、持っていた携帯電話をポケットにしまいながら、にやりと笑った。何ならこの債権、危ない筋に売ってもいいんですよ、と言われた二人は、その夜、頭を抱え込んだ。隆二がこしらえた借金は見る見るふくらんで、元利合わせて二百六十万円になる。
「そうだ、辰之を引き取ろう」
「こんな時に何言い出すのよ。姉が死んで、私たち、名前だけの身元引き受け人になったんでしょ?」
「まあ聞けよ。引き取るのにはここは手狭だろ?部屋を作るからと言って、施設が保管している辰の通帳、印鑑、カードの一切を受け取るんだよ。お前だって見ただろ?通帳には使う当てのない障害年金が貯まりに貯まって五百万だぞ、五百万。受け取ってしまってから、たまたまお前が体を壊して引き取れなくなったって、それは事情が変わったんだから仕方がない」
「し、施設をだますの?」
「いいんだよ。身内のことはそう簡単に罪にはならないし、施設は可哀想な障害者を絶対おっぽり出したりはしない」
次の週の火曜日の午後、施設の相談室を突然訪ねて来て、辰之を引き取りたいと申し出た叔母夫婦の態度に、修一は不審なものを感じた。
「実の母親が引き取れなかった辰之をですよ、一度も面会に来たことのない叔母夫婦が引き取るなんて不自然だとは思いませんか、施設長。辰之の部屋を作るからその前に通帳を渡せと言うのです。信用できませんよ」
興奮する修一に、ふむ、と施設長は腕を組み、
「恐らくカネ目当てだろうが、身元引受人だからなあ」
「しかし、年金は辰のもので、身元引受人のものじゃありませんよ」
「ましてや施設のものでもない。立場としては身元引受人の方が」
強いとおっしゃるのですか?と言おうとして、修一は言葉を飲み込んだ。そういえば市役所からは利用者の資産は極力預からないよう指導されている。
「何とかならないでしょうか」
と悔しがる修一に、
「成年後見制度しかないな」
施設長は聞き慣れない制度の名前を言った。裁判所が、意志能力の不十分な者に代わって意思決定や財産管理を行う権限を、信用できる人に与える制度だ が、四親等以内の親族か市町村長が裁判所に申し立てなければならないという。
「わかりました。親族は無理ですから、市役所にお願いしてみます」
早速修一が市役所で事情を説明すると、担当者からは的外れな返事が返って来た。
「必要なら叔母さんが申し立てたらどうでしょう。身元引受人の申し出を役所が根拠もなく悪意に理解する訳には行きませんからね」
終