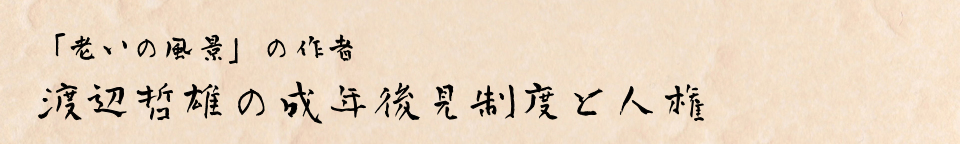- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 成年後見物語4
成年後見物語4
朝起きて目玉焼きでも作ろうかと握ったフライパンの手がすべり、うっかり大きな音でも立てようものなら、
「うるさいねえ!目が覚めるじゃないか」
客の前であくびする訳にはいかないんだからね、と襖の向こうから機嫌の悪い妻の声が聞こえて来る。
「何言ってんだ、あくびしたって、たかが酔っ払いの相手だろう。タクシーの運転手は眠ったら命取りなんだ。それでもだぞ、遅く帰って来たお前がテレビつけたり髪乾かしたりうるさくしても、俺が文句言ったことがあるか、バカ野郎!」
と言い返す元気は祥一にはない。出がけに喧嘩をすると一日中気分が悪いし、不景気で逆転した収入の差がそのまま夫婦の発言力の差になっていた。
「32号車、32号車、山上町2の1の辻井さん、銀行まで往復」
また近距離かと不満に思いながら、業務用無線に指示された場所に着くと、身なりのいい高齢の女性が立っていた。
大儀そうに後部座席に乗り込んだ女性は銀行の名を告げて、
「私、月に一度、年金を下ろしに行くのですけど、やまびこタクシーの運転手さんは不親切ですから、今日からあなたのところに変えたのですよ」
少し険しい顔をした。そしてすぐにうろたえて、
「あら大変、ガスを止めたかしら、運転手さん、私、ガスを止めたかしら」
ハンドバッグの中をまさぐり始めた。
「戻りましょうか?」
祥一が聞くと、
「いえ、ありましたから大丈夫です」
女性は家の鍵を見つけてほっとしたように前を向いている。
呆けているのだ。
やまびこタクシーは不親切なのではなくて、認知症の女性に付き合いきれなかったのに違いない。しかし逆に言えば、ちょっと親切にするだけで固定客になるということでもある。
銀行に着くと祥一はやさしく女性の手を引いた。女性はATMではなく、棚から払出し票を一枚取って書き始めたが、名前は書けても金額がうまく書けず、何枚も失敗したあげくすがるように祥一にペンを差し出した。
「七万円…ですね」
女性が名前を書き、祥一が金額を記入した払出し票に印鑑を押して窓口に出すと、苦もなく現金が下りた。
「通帳と印鑑、ここに入れますよ」
女性は月に一度、親切な運転手と一緒に銀行に行くのを楽しみにするようになった。
やがて女性の認知症は進み、買い物がおぼつかなくなった。
福祉関係者の努力によって、女性は金銭の管理を社会福祉協議会に任せる提案に同意したが、担当者は通帳を確認して驚いた。毎月きまって20万円ずつ引き出されているほかに、通帳の後ろに記帳されている定期預金が、数十万単位で不定期に下ろされて底をついていた。
「こんな大金、わずか二年間で何に使われたのですか?」
女性は被害を全く認識していないらしく、通帳の動きを指摘されても屈託なく笑っている。
その後、行員からの情報でタクシー運転手の関与が疑われたが、本人が出向き、本人が署名捺印した払出し票で手続きをしている以上、刑事事件としての立件は難しかった。
「辻井さんには土地や有価証券を含めるとまだまだ財産がありますが、本人の意思能力はどんどん衰えて行きます。金銭管理だけじゃなくて、本人に代わって総合的に権利擁護をする成年後見制度の利用を検討すべき段階だと思います」
会議では女性の今後について話し合われたが、恐らく世の中には似たようなお年寄りがたくさんいるのでしょうねという発言に,参加者の背中を寒いものが通り抜けた。
終