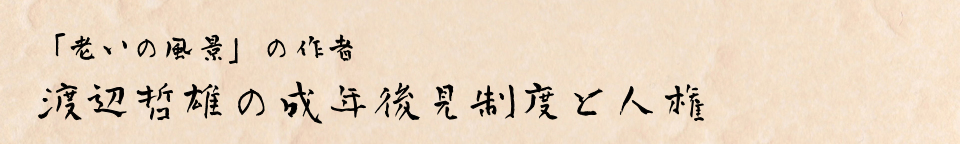- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 成年後見物語5
成年後見物語5
康男の泥酔ぶりを見かねて、
「今夜はその辺りでやめときなよ、ね?ヤッさん、飲み過ぎてんだからさ」
民子がカウンターの内側からたしなめたのが気に障った。
「何がやめときなだ、え?客だぞ俺は。客は飲むのが仕事、店は飲ませるのが仕事だろうが、バカ野郎」
もう一本つけろとばかり、康男が突き出した徳利が手を離れ、床で大きな音を立てた。その瞬間に民子の持っていたコップの水が康男の顔に飛んだ。
「帰っとくれ!」
数人の常連客が康男をにらみつけた。
こうなると康男はいくじがない。
「ち!」
よろりと立ち上がった。
「お勘定は四千二百円だよ」
康男はポケットから小銭ごと現金をわしづかみにしたが、千円ほど足りなかった。
「カネもないのにまだ飲むつもりだったのかい。うちはツケは効かないよ」
すぐに持っといでと言われた康男は、母親に叱られた小学生のように背中を丸めて店を出て行った。
「カミさんに死なれてから変になっちまったねえ、あの男」
「息子のカネなんだろ?市民病院の掃除やってる」
「ああいう子は真面目に働くけどねえ、わずかな給料、親父に飲まれちまうんだ。今に何か起きるよ」
可哀想に…と店でうわさしている頃、ごみ屋敷のような我が家に帰宅した康男は、居間に脱いである信司のジャンパーのポケットを無言でまさぐっていた。
「ん?」
信司がテレビから振り返ったときには、父親は息子のなけなしの小遣いを手に、
「ちくしょう、残りのカネを叩き付けてやるんだ」
暗がりの中を再び店に向かっている。
信司がコンビニのパンを盗んで捕まったのは次の週の日曜の午後のことだった。
交番に父親を呼んで説諭しても埒が開かず、父親の妹二人に連絡をしても、
「あの家のことにはもう…」
関わりたくないと拒否された警察は、
「空腹による犯行ですから、防犯というよりは福祉の問題ではないかということになりましてねえ…」
市役所の福祉課に話しを持ち込んだ。
担当者は頭を抱え込んだ。確かに息子には軽い知的障害がある。それは把握しているが、給料を奪う父親に対して役所は何ができるのだろうか。
通帳振込みにすれば通帳を奪われる。一週間ごとの小口支払いにすればその都度父親が取りに来る。息子にしか渡さないと断れば息子と一緒に取りに来る。
「…という具合で、雇用主も困り果てています。息子は職場で食べる昼食だけで、かろうじて命をつないでいるようなものですよ」
担当者の報告を聞いた新任の係長は、
「それは君、明らかに父親による虐待だよ。本人を施設で保護した方がよかないか?」
責任取らされるのはごめんだよという顔をした。
「程度が軽すぎて施設入所は無理ですよ」
担当者はため息をついて、
「こういう場合、裁判所に申し立てて、本人に代わって財産を管理する権限を第三者に与える成年後見という制度があるにはあるのですが…」
「利用できないのかね?」
「申し立てる親族も引き受ける親族もいませんよ」
「ふむ…まあ、そうだろうな…」
「市長が申し立てることもできますが…」
「が?」
「こんな厄介な案件を安い報酬で引き受けてくれる専門職はいませんからねえ…」
「結局、支払い能力のない人間の権利擁護はできないということか」
「最近、自治体が人件費を負担して、成年後見事業を委託するNPO法人ができ始めていますが、費用を負担している自治体の住民だけが対象です。残念ながらうちは負担していませんし、負担する予定もありません」
「制度はあっても使えないという訳か…」
係長は費用もかけないで人間の権利擁護ができると考えている安易な市の姿勢に初めて問題を感じていた。
終