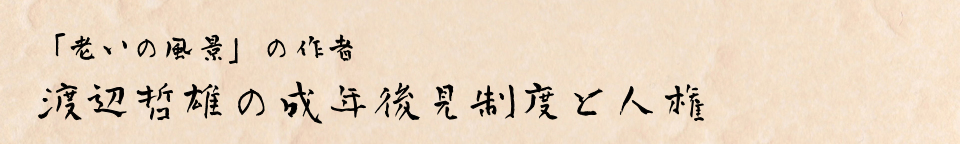- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 成年後見物語6(最終回)
成年後見物語6(最終回)
焼香する参列者を見て、何かを食べていると勘違いした忠雄が抹香を口に入れようとするのを、
「食べたらあかん!」
抱き抱えるようにして制止した静子はその場に泣き崩れた。五十歳にもなって焼香の意味さえ分からない息子と二人、これから先どうやって生きて行くのだろう。不安は静子の心を蝕んで、やがて親戚の名前すらおぼつかなくなり、四十九日の法要は義弟の公雄が取り仕切った。
「義姉さん、うちのとも相談したんやけどな、この家は維持管理だけでも大変やから、環境のいい田舎にマンション探して移った方がいい。しばらくは和代も一緒に住んで面倒をみるつもりや」
そやろ?と促されて、
「二人きりの姉妹やさかい、助け合わんとな」
そう答えた和代の言葉が嬉しくて、静子は夢中でうなずいた。すぐに親切な不動産屋と司法書士を探して来た公男は、役所にも銀行の窓口にも付き添って、難しい不動産売買や登記の手続きを全部やってくれた。静子は傍らで聞かれることに「はい」と言っていればよかった。
それから二ヶ月・・・。
マンションの五階の窓に広がる田舎の風景は美しかったが、通帳も印鑑も管理してこの家に君臨する和代のことを静子は時々誰だかわからなくなった。
認知症の母親と知的障害者の息子がバスに乗ったまま途方に暮れているところを保護されたのは、それから半年後のことだった。
「いえね、田舎に越した姉が心配でしばらく面倒見てましたけど、ボケたんですね、突然えらい剣幕で顔も見とうない言い出したんですよ」
警察からの電話に和代はそう説明し、
「もう一切関わるつもりはありませんから」
あとはお任せしますと言った。
静子に選任された成年後見人が資産を調べると、一等地の家屋敷を売却した八千万円と、マンションを購入した三千万円の差額が不明であるだけでなく、静子の通帳の定期預金は残らず引き出されていた。
終