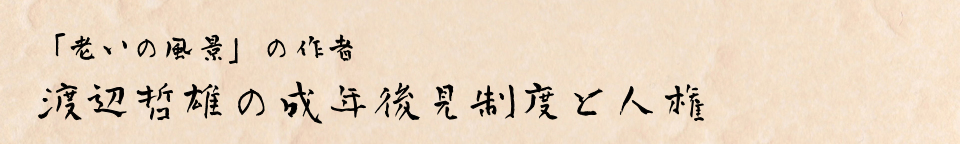- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 委任契約の闇
委任契約の闇
民子が居室を間違えるだけでなく、間違えた部屋の住人の持ち物と自分の物との区別ができなくなると、フロアの苦情は一気に表面化した。
「施設長、彼女の状態は養護老人ホームの限界を越えています」
認知症高齢者専用の施設に移すべきだという職員会議の結論に従って、施設長はグループホームを探すよう命じたが、
「ようやく空きを見つけたグループホームが身元保証人を要求するんですよ」
担当職員は困り果てていた。
「うちの施設の保証人にそのまま引き受けてもらえばいいだろう」
「妹さんは、二年前に亡くなりましたよ」
「ん?…ということは、うちは身元保証のないまま入所を継続していたのかね?」
「養護老人ホームの入所は行政の措置ですからね。ま、親方日の丸って言うんですか、保証人なんかなくったって、入院でも死亡でも最終的には市が責任を持ってくれますが…」
「介護保険適用のグループホームは、本人と施設との契約で入所するから、身元保証人が要るという訳か」
「しかしですよ、施設長。保証人といっても、本人に結婚歴はありませんし、妹さんの二人の子供たちも引き受けるつもりはありません」
「確かに、今どき、叔母の面倒まで見ろというのは無理があるよなあ」
「日常生活自立支援事業も成年後見制度も、福祉サービスの契約の支援や財産管理はしてくれますが、身元保証はできないそうで…」
「ふむ…」
施設長はしばらく天井を仰いでいだが、思い出したように机から名刺のフアイルを取り出して、
「民子さんに財産はあるのかね?」
と聞いた。
養護老人ホームへの入所は低所得であることが条件だが、生活保護ではないから保有財産に関しては条件が甘い。国民年金以外に収入のない民子は十分に条件を満たしていたが、別に若い頃からこつこつと蓄えた預貯金や有価証券のたぐいがざっと二千万円と、駅前の便利な場所に、廃屋同然の木造家屋の建つ土地を所有していて、通帳や関係書類は全て施設で保管していた。
「それだけ資産があるのなら、一度ここに連絡を取ってみたらどうかね?」
施設長が探し出した名刺には、身元保証から財産管理、葬儀や墓石の購入までを有償で引き受ける団体の名前が書かれていた。
「ほう…今はこういうことがビジネスになるのですね」
その週の金曜日にやって来た背広姿の二人の男性は、ご連絡ありがとうございますと慇懃に挨拶をしたあとで、
「それでは早速ですが、ご本人をお連れ頂けますか?あ、印鑑もお願いしますね」
アタッシュケースから何やら書類を取り出しながら言った。
「連れて来るのは構いませんが、認知症ですから、まともな会話は期待できませんよ」
「いえ、慣れておりますので」
職員に伴われて会議室にやって来た民子を見るなり、
「ああ、民子さんですね?お元気そうで何よりでした」
二人の男たちは満面に笑みを浮かべて立ち上がった。
それから三十分も経っただろうか、
「では民子さん、安心して万事私どもにお任せ下さいね」
男たちに抱きかかえられるようにして会議室を出てきた民子は、嬉しそうに二人に頭を下げた。
「お蔭さまで無事ご本人との委任契約が成立致しましたので、保証人を含めたグループホームへの入所手続きは私どもの方で致します」
男の一人は施設長に報告をしたあとで、
「あ、それから、これまで施設の方でなさっていた財産管理も私どもに任されましたので、ご本人所有の通帳その他を引き継がせて頂きます」
と言った。
分かってはいたものの、いざ一人のお年寄りの財産の一切を引き渡すとなると、この団体を信用していいものかどうか施設長はにわかに不安になった。
「あの、ご本人用の契約書は…」
「もちろん大切な書類ですので、私どもでしっかりと保管致します」
「しかし契約書は双方が持つものでは…」
と言おうとして施設長は口をつぐんだ。民子に保管能力はない。しかし、双方の契約書を一方だけが保管するのは不適切ではないか。財産を任せた側に十分な判断能力がなく、しかもこれからどんどん悪化するというのに、契約書は二通とも財産を預かる側が保管して、監視する第三者もいないのだ。
ひょっとすると自分は今、とんでもないビジネスを仲介しているのかも知れないと施設長は思った。本来なら面倒でも裁判所の監督の下で本人の意思を代弁する成年後見制度を利用した上で、後見人と団体の間で保証人契約を結ぶべきだったのだ。
「あの、財産をお渡しする責任上、一応、契約書を拝見させて頂きたいのですが…」
そう申し出て目を通した委任契約書は、民子を「甲」と呼び、団体を「乙」と呼ぶ堂々たるもので、あらゆる誤解から身を守るようにいかめしい文章が並んでいたが、施設長が読んでも難解な契約文書を民子が理解したとは思えない。末尾には、団体の立派な角印と並んで、小学生のような民子の署名と小さな印が押してあった。
その三日後、民子は迎えに来た団体の車の後部座席で手を振りながらグループホームに移って行った。
「これでよかったんだろうか…」
見送りながら施設長が言った。
「うちは限界でしたよ、施設長」
「いや、あの団体に依頼したことだよ」
保証人費用が二十五万円。今日のような車での送迎にも当然ながら費用が発生する。葬儀や墓石の手配は言うまでもないが、契約書にはたった一行、本人が死亡した場合、全ての慰留金品や財産は団体に寄付をし、団体はこれを受諾するという条項が記載されていた。
「それって、遺言ですよね」
「いや、私も気になって調べてみたが、遺言は原則自筆で書くことが必要なのだが、あれは死因贈与契約と言って、印鑑が押してあれば印字の文書で有効なんだそうだ」
二人の脳裏には民子の預貯金と所有する駅前の土地が浮かんだが、
「施設長、そこから先を考えるのは止めましょう。うちは無事彼女がグループホームに移ってくれればいいのですから」
担当職員はそう言って民子を団体に引き継ぐための書類の整理にとりかった。
終