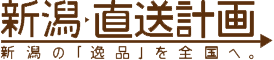逸見酒造(有) Itsumi Shuzo Co.,Ltd. 佐渡市
| 1872(明治5)年、佐渡島真野町で創業、佐渡で一番小さな蔵元。農業を稼業としていた初代がその米を加工したのが始まり。 酒造りに必要不可欠な水は敷地内の井戸水。かつて遠浅の海底だった蔵のある場所は、地下に貝殻の堆積層があり、その層で濾過された水。適度にミネラルを含む中硬水を使うことでどっしりとした味わいの酒になる。 酒米は山田錦が2割。越淡麗と五百万石が6割。加工用米が2割。酒造好適米という専用の酒米を使う。米を蒸しその蒸し米に麹を加えてからは、手作業で五感を研ぎ澄ませて向き合う。 県下でも数軒しか扱っていない山廃仕込みの酒。古い製法で、全行程を手作りで行って手間もかかるが、佐渡の地酒として特色ある位置づけができる酒だ。 端麗辛口のスッキリとした飲みやすい酒というよりも、米本来の味わいを生かした旨みのある酒が特徴。 酒名「真稜」の由来については「順徳上皇真野御陵」を命名の由来に持つ。 「至」は、フルーティーで爽やかな飲み応えの日本酒として、テレビ放送「嵐にしやがれ(日本テレビ)」で紹介されて一時は手に入らないほどのブームとなった。 「至」の商品名は最初は「真稜 純米吟醸酒」だったが、数年前に地元の酒販店から「何かネーミングを」との要望を受け、酒販店とともに考えて命名。旧真野町長を務めた先々代の名前に由来する。
🔶逸見酒造の飲める店
逸見酒造  地図 地図
 ストリートビュー ストリートビュー
|
|
逸見酒造の検索結果    新潟県の逸見酒造に関連するお店  (一口メモ)
花見酒源氏物語にはすでに桜を愛でて詩歌を詠む宴の様子が描かれていて、古くから日本人は桜を愛していたことがうかがえる。昔から、桜の木には田の神様が宿るとされ、農民は、豊作を願い供え物をしていた。神様に捧げるために造られた日本酒は、お祝いの飲み物として重宝された。 史上最も有名な花見は1598年(慶長3)年3月豊臣秀吉が開いた京都醍醐寺の花見と言われる。江戸時代に入ると、三代将軍の徳川家光が、隅田川の河畔や上野に桜を植えたのは有名な話。桜を見ながら日本酒を飲みにぎやかに宴会をすることが、春の行楽行事として庶民に定着した。 |
|
|
|
|
|
|
|
|