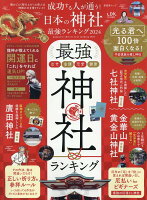白山神社 Hakusan Shrine 糸魚川市
|
畠山義元
能生白山神社は、能生駅の北西約1.2㎞、街の東端にある権現山にあり、ここは神社の森で、古くから「尾山の森」と呼ばれていて、その中腹に存する。?〔生〕~永正12年10月20日(1515年11月25日)〔没〕 能登の守護大名 明応9年(1500)に弟の畠山慶致を擁立しようとする守護代・遊佐統秀らに謀反を起こされて、越後に追放されたが、後守護に復帰している。 崇神天皇の11年11月(紀元前66年)の鎮座と伝えられる。能生郷草創以来の奴奈川神社だった。 奈良時代に、「越の大徳」こと泰澄大師(682~767)が来住して、社殿を造立し、修験道の道場として社観を整え名前を「白山権現」と改めたたという。延喜式内社の奴奈川神社は、当社のことと言われている。 明応年間(1492~1501)火災で焼失。永正年間(1504~21)に再興された。 神域は広々として閑静で、木々に囲まれて、拝殿は入母屋茅葺である。三間社流造の本殿は尾山の下に食い込むように建てられ、棟札、墨書などから、永世12年(1515)、能登守護畠山義元が造立寄進し建立とされる。東側の軒の出が短く、縁を省いた非対称形が印象的で室町時代のたたずまいを色濃く残す。 和様形式を主体とした手法の中に、組み物には唐様形式のヒジ木を使っているのが特徴だ。江戸、明治、大正と修理を経て「昭和の大修理」は、2年がかりで大掛かりな解体修理を行った。昭和33年(1958)3月、本殿が国の重要文化財(建造物)に指定された。 神社背後の小丘(通称尾山)を覆って茂り合う社叢は国指定の天然記念物に指定されている。またそこに生息するヒメハルゼミの北限の地として知られ、ヒメハルゼミは国の天然記念物として保護されている。 上杉謙信から太刀一振りと社領二百貫の寄進があったが、近世初期、上杉氏に代わって春日山城主となった堀秀治に社領を没収されて一時衰えた。徳川幕府から朱印50石が寄せられて復興された。 本殿脇には青銅色に光る龍が異彩を放つ。その口からあふれる水は県の名水百選「竜の口の名水」。水源は長野の戸隠神社奥社の池と伝えられる。龍の頭が戸隠、胴が妙高山、尾が白山神社の尾山。山岳信仰に支えられたロマンも漂う。 神社は多くの重要無形文化財を所有、なかでも、明治の神仏分離で廃された別当寺の宝光院から移安された、平安後期の作の木造聖観音立像は像高1・4メートルと小ぶりながら桜材の特徴を見事に生かし、清楚にして貴品あふれるつくりは藤原期彫刻の特徴を十分煮生かしている。明応8年(1499)在銘の釣り鐘や、海上信仰資料の一級品、安永6年(1777)銘の国内唯一の「はがせ船」が描かれた絵馬がある。県指定の文化財に指定されている。 鎌倉時代には源義経が武運長久祈願をして立ち寄ったとも伝えられ、元禄2年(1689)7月11日、曾良とともにここを訪れた松尾芭蕉の「曙や霧にうつまくかねの声」の名句が生まれ、江戸時代後期の文政5年(1822)年建立の句碑が建つ。 4月の白山神社春季大祭には、国指定重要無形民俗文化財の舞楽が上演され、遠近からの参拝、見物客でにぎわう。 平成8年(1996)、環境庁の日本の音風景百選に裏山に生息するヒメハルゼミが選ばれたのを機に、町は鳴き声の聞こえる7月下旬に「姫春蝉俳句大会」を境内を主会場に開催している。
🌌白山神社社叢社殿の東側に盛り上がる尾根一帯、通称・尾山で、内陸側斜面には、常緑樹のアカガシなど南方系の樹木がうっそうと生い茂る。標高90mほどの尾山に3.5ヘクタールにわたって残る白山神社社叢は、暖地性の樹種が杉、松など寒地性樹種と共生する、北越海岸南部における植物分布を知るうえで貴重とされている。 境内から社叢に足を踏み入れると、足元のオオバノハチジョウシダ、フモトシダなど多彩な暖地性シダは日本海側の自生地の北限とされる。 アカガシ、タブノキ、シロダモ、ヤブツバキなどの常緑樹が主で、ケヤキ、エゾイタヤ、ミズナラ、ホオノキなどの落葉樹が存する。350種を超える植物が生育しているとされる。 こうした森は暖かい対馬海流のたまものだ。暖流の流れに沿って、かつては日本海沿岸にこうした森が点在していた。だが堅いアカガシは幅広い用途があるため、近代までに次々と伐採されていった。県内でも多くは船の櫓をつくるために切られてしまったりした。 これだけの森がが手つかずで残されたのは、信仰の対象だったためだ。県内ではここと、佐渡に残るくらいだ。地元の人々は必要な薪を別の山にとりに行った。ここでは一本一草も傷つけてはならないとされてきた。 昭和12年(1937)に国の天然記念物に指定された。 🌌能生ヒメハルゼミ発生地尾山特融のヒメハルゼミは白山神社を本州北限とする。南方系のセミで、体長27mm、翅端まで36mmあまり。我が国のセミの中では最小と言われている。優しい感じがするので、名づけられたという。尾山には、アカガシをはじめヤブツバキ、シロダモなど暖地性の常緑広葉樹が多く、生息に適している。 特異な鳴き方をすることでも知られている。単独では鳴かずに数十匹が一斉に声をそろえ鳴きだすと、その鳴き声に合わせて他のセミが鳴きだし、しばらく鳴いた後、申し合わせたようにハタと止むのが不思議とされている。その繰り返しが音律的で、環境庁の「日本の音風景百選」にも選ばれている。小さな体ながら、鳴き声は大きく、社叢を包み込むように響き渡る。 また、社叢はうっそうと生い茂る樹木が密生して、昼でも暗いため、午後3時ごろからヒメハルゼミの羽化が始まる。その様子は神秘的である。 昭和17年(1942)、国の天然記念物に指定。平成8年(1996)7月、環境庁の「残したい音風景100選」に尾山のヒメハルゼミが選ばれた。 🌌白山神社の海上信仰資料能生町は、江戸時代から明治期まで30ほどの小さな廻船問屋が軒を連ねていた。白山神社は総鎮守であり、海の守り神。船主や船頭が航海の安全を祈り、無事に帰ってきた感謝を込めて数多くの船絵馬を奉納した。年代が判明している最も古いものは宝暦2年(1752)の「権現丸」で、このほか多数保管されている。注目されるのは、縦1m、横1.5mほどの「はがせ船」の船絵馬である。「はがせ船」は「北前船」の前身として江戸中期まで日本海の主力船として活躍したが、絵馬は国内で唯一ここだけに現存する。岩礁が多い北陸沿岸の航行には適するよう船底が平らで丈夫な造り。船尾のかたちが、鳥の左右の羽が重なる様子(羽交い)に似ているので、こう呼ばれた。 船絵馬が発見されたのは、昭和20年代。拝殿の屋根裏で発見したのがきっかけだった。 船絵馬93点、船額4点は海上信仰資料として昭和62年(1987)3月に国の重要有形民俗文化財に指定された。文化庁が平成2年(1990)から3年間かけて修復作業が行われた結果、色鮮やかによみがえり、宝物殿に納められた。 普段は閉鎖されているが、町教育委員会に申し込めば見学できる。 🌌蛇の口の水
🌌白山神社春季大祭
|
 白山神社
白山神社  白山神社社叢
白山神社社叢