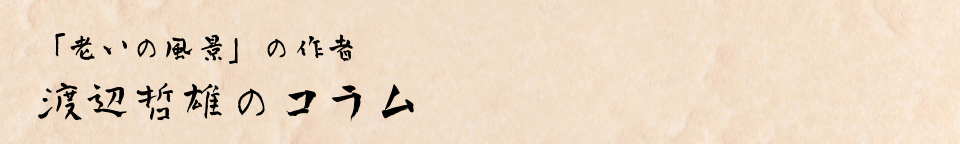- ホーム > 平成16年掲載コラム/目次 > 安心と自己責任
安心と自己責任
平成16年04月29日
イラクにおける人質事件は、日本国家のイラクに対する関与の仕方というよりも、民間人が危険な地域で社会的活動を行う場合の自己責任について国民的な議論を巻き起こしました。事態が国家間の政治的な舞台に上がってしまうと、様々な立場からの議論が可能になりますが、私は社会保障につながる「安心」という観点から、自己責任と国家との関連について考えてみたいと思います。
私には倉敷に嫁いだ娘がいます。昨年の七月に嫁ぎ先で長男を出産しました。私にとっては初孫ということになります。予定日を過ぎてからというものは、毎日が期待と不安の連続でした。いよいよおれにも孫ができる…という無邪気な期待の内容を無理やり言葉にすれば、私という人間の生命の糸が、もうひと世代かなたまでつながることに対する厳かな喜びとでも言うのでしょうか。自分の子どもが生まれた時と比べると、孫の方がわずかに抽象的で距離のある期待感でした。
一方、不安の方は昔から同じです。五体満足で生まれて来て欲しい…。障害を持っている人たちに対してある種の後ろめたさを感じながら、私は祈り続けました。脳性麻痺、先天性疾患、奇形、欠損、発達遅滞、難聴…。
突然襲う人生のアクシデントをこれまでたくさん見てきた分、不安は娘夫婦より大きいのでしょう。高じると想像は悪い方に転がり始めます。生まれた子どもに障害がある。悲歎を乗り越えるより先に、悲嘆の温度差に負けた娘夫婦がいさかいを繰り返した末破綻する。孫を抱えた娘が戻って来る。やがて取り持つ人があって、ためらう娘を無理やり再婚させる。私の手元に障害児が残る。心労がたたって私が病む。夫と孫の世話に疲れた妻が倒れる。そんな馬鹿なことを…と笑い飛ばせない落とし穴が現実にはたくさんあることを、五十年も生きてくると知っているのです。
そう思って改めて日常を振り返ると、人生は薄氷を踏むような不安に満ち満ちていることが解ります。病気、事故、倒産、失業、天災、火事、犯罪被害…。自分一代限りの視野で考える訳にはいきません。子に、孫に、ひ孫に…と思いを馳せれば、どこかの代で私の遺伝子は間違いなく何らかの困難に直面することでしょう。その範囲に人質事件を含めてもいいように思うのです。
人生は薄氷を踏むような不安に満ちていると書きましたが、薄氷とは、個人で備えるには限界がある出来事を指しているのではないでしょうか。文明社会の歴史は、踏んだ薄氷が割れた場合の不安に、構成員相互の連帯で対処しようという営みとしてとらえることが可能です。税で、あるいは保険料で、安心を担保する知恵を積み重ねて、私たちは今日の国家責任や社会保障の仕組みを構築しました。それが人口バランスの変化に対応して根本的な変更を迫られています。そこへ人質事件を契機に自己責任の議論が浮上したのです。
避難勧告の出ている地域に自らの意志で出かけて行った国民の救出費用が自己責任であれば、神戸の震災に駆けつけて二次災害に巻きこまれたボランティアやフリーライターの救出費用だって自己責任が問われます。高齢出産の危険を承知で産んだダウン症児の療育費用は自己責任だとか、ヘビースモーカーが肺癌になった場合の治療費は自己責任だとかいう議論に発展すれば、私たちは薄氷を踏んだら生きてはいられません。
自衛隊を退く退かないは別の政治的問題です。今後イラクへの民間人の入国を制限するしないもここでは論じません。ただ、営々と築き上げて来た国家責任や社会保障の外堀が、自己責任の四文字を盾に埋められることを警戒しています。
幸い孫はいたって健康で誕生しました。しかし彼が、あるいは彼の子どもが、正義感からであるにせよ、不注意であるにせよ、生命の危険にさらされて個人の力の及ばない時は、最善を尽くして救済が試みられる体制の国家であってほしいと願わずにはいられないのです。
終