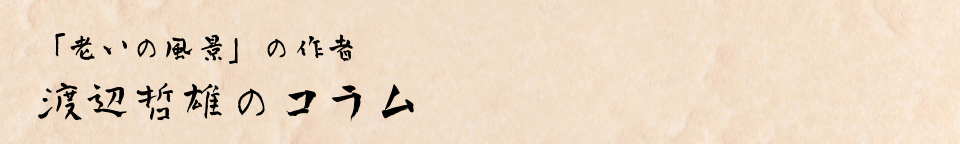- ホーム > 平成16年掲載コラム/目次 > 追憶(紙芝居)
追憶(紙芝居)
平成16年06月10日
同じ時代を生きた者たちだけが共有する子供の頃の懐かしい風物を、記憶をたどっては書き留めておこうと思い立ちました。
私が生まれ育った郡上八幡は、一つの家から火が出れば、町中が灰になるほど民家の密集する奥美濃の城下町ですから、移動販売には都合がよかったのでしょう。今では落語の世界にしか登場しないような「もの売り」の姿があちこちで見られました。
涼しげな金魚の入った木製のタライ二つを天秤棒で振り分けて、水をこぼさないように巧みにバランスをとりながら売り歩く「金魚売り」の売り声は、家の中で聞いているだけで心にサアッとかすかな風がよぎりました。
大きな缶の中で固まっている透明な飴を、先の尖った金属の筒で、シャッ、シャッと雪のように削って、三角に丸めた紙の中に勢いよく入れてくれる「削り飴売り」は、売り声の代わりにリヤカーの上で団扇太鼓を叩いて子供たちを集めていました。砂糖で味をつけたほのかに甘いうどん粉を鉄板の上でクレープのように円く薄く焼いて、注文どおりの動物の絵を素早く食紅で描いてくれた食べものは、何と呼ばれていたか思い出せませんが、ちょうどラーメン屋のような構造の屋台を黒い頑丈な自転車で引いていました。風が吹くと、木枠に吊り下げられたたくさんのガラスの風鈴が、小鳥の大群のようにチロチロと鳴り続ける「風鈴売り」のリヤカーは、風が止むとピタリと静かになって、もう一度音を聞きたい客たちの足を引きとめていました。
子供たちはわずかなお小遣いを握りしめて「もの売り」の周りを取り囲んでは、買おうか買うまいかさんざんに迷ったものですが、誰もが迷わずにおカネを支払ったのが「紙芝居」でした。十円でねり飴を買うのがいわば入場料で、短い割り箸の先につけてもらった水飴をくるくるくねくね、練って練って、気泡で真っ白になるまで練りながら待つうちに、目当ての人数が集まったのを見計らって、麦わら帽子に綿シャツ姿のおじさんが、よく通るダミ声で紙芝居を始めます。独特の口調で語られる「バットマン」や「スーパーマン」を、子供たちはねり飴をなめながら立ったまま聴くのですが、中にきまって一人、飴を買わないで紙芝居を見ようとする不心得者がいました。家庭が貧しくて小遣いがもらえない、今思えば気の毒な子供だったのですが、
「おめえ、飴買わずに見たらあかんぞ」
冷たく排除したのは紙芝居のおじさんではなくて子供たちでした。不正を憎んだのではありません。紙芝居見たさに誰もがなけなしのおカネをはたいて飴を買うのです。ただで見られたのでは何だか自分たちが損をするような、あさましい感情の仕業でした。
自転車の荷台の上に置かれた金色の額縁の中で、抜き取られる度に場面を変える紙芝居の絵は、妙に鮮やかな極彩色で記憶に残っています。ストーリーはすっかり忘れてしまったくせに、主人公が危機にさらされる一番いいところで次回に続くもどかしさだけはくっきりと覚えています。しかし、いつも仲間たちから排除されたあの貧しい子供は大人になって、いったいどんなふうに紙芝居を思い出すのでしょう。私にとっては懐かしい紙芝居ですが、ひょっとすると彼にとっては一番思いだしたくない、いまいましい想い出なのかも知れません。
終