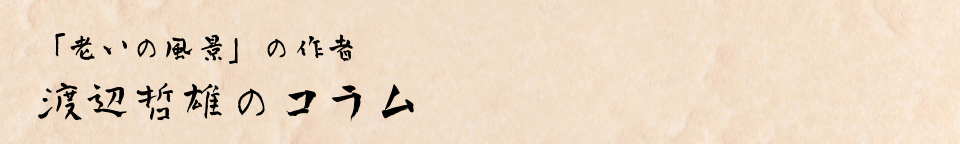- ホーム > 平成16年掲載コラム/目次 > 追憶(映画)
追憶(映画)
平成16年06月10日
昭和二十五年生まれの私が小学生の頃は、よく学校に映画が来ました。講堂のステージにスクリーンを張れば、にわか仕立ての映画館のできあがりです。館内を暗くするために窓という窓に裏地の真っ黒なカーテンを閉めました。これがきちんと閉めてなくて風でめくれたりすると、外の光が突然差し込んで、映画の世界に浸りきっている気持があっけなく現実に引き戻されたのを覚えています。なあんだ、外には昨日と同じ鉄棒や砂場があるんだ…。あの、夢から覚めるような、あるいは手品の種明かしを見たようながっかりした安心感は、射し込んだ光と同じくらい鮮やかな印象で心に焼き付いています。
映画は決まって丸で囲まれたキズだらけの数字が十…九…八…と秒読みのようにスクリーンいっぱいに映し出されて始まりました。子供たちはロケットの打ち上げのように、声を揃えてそれを読み上げたものでした。もちろん学校ですから、映画は教育的なものばかりでした。内容の記憶は断片的ですが、『つづりかた教室』とか『トタンの穴は星のよう』というタイトルを覚えています。どれも子供が主人公で、おしなべて貧しく、兄弟がたくさんいて、健気に生きている主人公が病気で死んでしまうストーリーだったように思います。拾って来た子犬を父親から捨ててしまえと言われて捨てることができず、川原に小屋を作ってせっせと食べものを運んでいた少年が、台風の中を濡れながら犬を助けに行って肺炎で死んでしまう話は、小学校の低学年で見た映画にもかかわらず、耳を澄ませば激しい雨音が聞こえそうなくらい今も印象は鮮明です。
そんな中に、鉛筆泥棒の疑いでいじめられる少女の映画がありました。結局少女は、ひとが捨てたチビた鉛筆をこっそり拾っては持ち帰り、可愛い人形をこしらえていたのですが、不用品をコケシとして蘇らせる少女の夢と愛情が、ひとつひとつ表情の違うおびただしい数の鉛筆コケシの愛くるしさと重なって、観る者の胸を打ちました。すぐに子供たちの間で鉛筆を利用した人形造りが流行りました。しかし、流行に夢中になった子供たちのエネルギーが方向を失うのは、今も昔も変わりはありません。最初のうちは映画の精神を汲んで、短くて使えなくなった鉛筆で人形を作っていた子供たちは、やがて、まだ新しい鉛筆をわざわざ切ってこしらえるようになりました。男の子は人形ではあきたらず、野球のバッドを作りました。小刀であらかたの形を削り、あとは丹念にサンドペーパーで整えます。先生の目を盗んで、授業中にバッドを磨いているのを見咎められるに至って、鉛筆を用いた子供たちの造形活動はとうとう禁止されてしまいました。今では鉛筆はシャープペンシルに変わり、小刀など使ったことのない子供たちがテレビゲームに夢中です。しかし私は鉛筆を見る度に、時間を忘れてサンドペーパーを使った時の、あの高揚した気分と、スクリーンいっぱいに映し出された無邪気なコケシたちの顔を思い出しては、時代というものの持つ圧倒的な力について思いを巡らすのです。
終