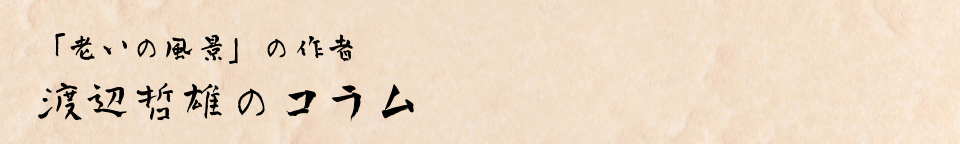- ホーム > 平成16年掲載コラム/目次 > 花火
花火
平成16年08月03日
八月の声を聞く頃になると、あちこちで花火大会が盛んですが、私は毎年八月一日に開催される美濃市の花火が好きです。そんなに規模が大きくありませんからシャトルバスなども出ず、地元の人はくつろいだ格好でぶらぶらと歩いて会場に向かいます。少し遠方の人は市役所や商店街や銀行の駐車場に車を置いて長良川河畔まで歩きます。国道の東側には、電柱を地下に埋め石畳を敷き詰めて、町並みの美観に予算をかけた「うだつ」の町が広がっていて有名ですが、西側は変哲もない民家の密集する数本の細い坂道が、どれも長良川に向かってだらだらと続いているだけで、普段は訪れる人もありません。ところが花火の夜だけはこの坂道が主役になるのです。
坂道の両側に連なる民家には、軒ごとに、鈴なりのホオズキ提灯をつけた背の高い笹竹が立てられて、一斉に灯が入った時の美しさは言葉になりません。ぼうっと滲む赤い提灯の群れが点々と続く坂道を、宵闇の中に、もはやこの世の顔を失った人々の影だけがひしめき合いながら下りていく様子は、ひょっとするとその先に、ぽっかりと死んだ人たちの世界が広がっているような幻想に駆られます。
江戸の昔には、川を行き交う荷物舟の安全を見守ったという木製の灯台が、巨大な黒い袴を履いたように裾を広げてそびえ立つ堤防の一帯が花火見物には格好の場所です。
そこへ今回は、私一人で出かけて行って後悔したのです。
湊(みなと)町という名のとおり、それまで瀬音を立てて海を目指して来た長良川が、ゆったりと淀みを作って一休みしたその辺りは、日中は水遊びに興じる家族連れで賑わうところなのですが、今はおびただしい数の見物客たちが埋め尽くして、花火が始まるのを今や遅しと待っています。屋台で買った焼きソバやたこ焼きをつまみに、あるいは缶ビールを、あるいはコーラを飲みながら、仲間が家族が恋人が楽しそうに談笑する中で、私一人が無言です。やがて本部席のスピーカーが女性の声で、花火大会を開催するための資金を提供した会社や個人の名前を延々と読み上げ始めると、
「おい、いつまでつまんねえ名前読んでんだ?いい加減に始めたらどうなんだ」
「まあそう言うな。あの人たちのおかげで俺たち花火が見えるんじゃないか」
「確かにな。一瞬で消える花火のために安くもないカネを払ったスポンサーとしては、せめて名前ぐらい呼んでもらわなきゃやりきれないだろうよ」
「それにしても長いよな…。うんざりだぜ」
若者のグループの会話が聞こえても、
「そうだ、そうだ!」
と言いたい気持を私は我慢しなければなりません。見知らぬおじさんが突然会話に加わるのは不自然です。そうこうしているうちに、花火が始まって、息をのむようなスターマインや、夜空一面に広がる菊の大輪に、
「うわあ、綺麗!」
「すげえなあ!」
河川敷のあちこちで感動の声が上がっても、私だけは無言です。一人で素直に驚きの声を上げるのがどんなに勇気の要ることかということを、その時私は初めて思い知りました。
どうやら人間は感動を誰かに伝え得てようやく充足するもののようです。一時間に及ぶ花火大会を終始無言で見物した私の心には、ギャラリーのいないステージでカラオケを熱唱した時のような言い知れぬ虚しさが広がっていました。うわあ綺麗!などという言葉は独り言に属していると思っていたのは間違いでした。人間は聞いてくれる人の存在を意識しなければ感嘆の言葉一つ発することが難しいのです。孤独でした。一人で本を読むことも、一人で旅をすることも、一人で酒を飲むことも苦にはならないのですが、花火は一人で見るものではないと思いました。恐らくお化け屋敷も一人で行くところではないでしょう。遊園地も一人では楽しめないでしょう。要するに一定限度を越えた感情の内圧を処理するためには、どうしても受け止めてくれる相手が要るのです。多感であればあるほど日常のささやかな出来事にも心が揺れて、感情の内圧が高まる機会が多いのですから、受け止めてくれる相手も結果的に多彩です。多感が多情に通じるのには理由があったのか…と、ここまで考えてきて、私は改めて自分の母親が故郷で一人暮らしであることに気がつきました。庭に見知らぬ鳥が舞い下りても、近所に火事があっても、切り倒した柿の木から新しい芽が伸びても、その感動を伝える相手がいないまま布団にもぐりこむ毎日はどんなにか淋しいものでしょう。
「一人には慣れているからねえ…」
きっと彼女はそう言って笑うに違いありませんが、決して慣れてはいけないことのように思います。話し相手にならなければと思いました。そして待てよ…私には話し相手がいるのだろうかと自問したとたん、不覚にもわずかにうろたえました。一緒に暮らす人はいても、随分長い間、自分がさっきまでの花火会場にいるような気がしたのです。
ホオズキ提灯の揺れる坂道を逃げるように上り切って振り返ると、顔のない人々の群れが引きも切らずひしめき合っているのでした。
終