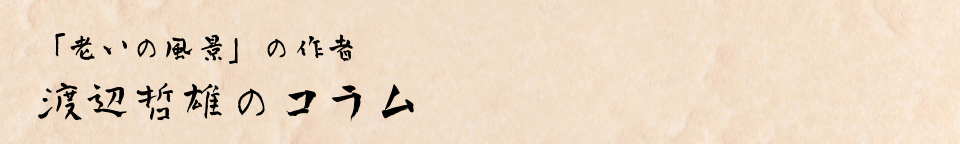- ホーム > 平成16年掲載コラム/目次 > 経済問題としての男女共同参画
経済問題としての男女共同参画
平成16年08月19日
男女共同参画社会の実現のために方々で様々な取り組みが行われていて、最近では私のところにまで講演依頼が舞い込むようになりましたが、たいていの主催者が控え室でこんな本音をもらします。
「男らしさや女らしさを否定することに露骨に抵抗を示す人も増えていましてね…」
「固定的な男女の役割を見直そうという問題は、総論は賛成でも各論になると色々と考えが違うようで…」
「男も女も性別に関係なく個性を発揮して自分を実現できる社会を作ろうというのですから異論はないはずなのに、ここに来て今ひとつ盛り上がらないのですよ」
つまり主催者は、この問題を女性の人権擁護とか差別意識に関する精神運動として展開して行き詰っているのです。
男女共同参画社会は、少子高齢化という人口構造の変化と、成熟した経済のグローバル化に対応する労働力確保対策の一環として登場したものであることを認識しない限り行き詰まります。そこで講師としての私の仕事は、男らしさ女らしさに関する固定的な観念を意識から払拭しようとすることがいかに無謀な試みであるかということを立証して見せることから始まるのです。
「ここは深夜の警察署です。あなたは係長。部下は出払っていて、若い男性警察官と女性警察官が一人ずつ残っています。そこへ二本の外線が入ります。一つは窃盗、一つは刃物を振り回しての喧嘩です。係長であるあなたが男性の部下を喧嘩に、女性の部下を窃盗に派遣しようとすると、男性の部下がこう抗議するのです。係長、前回私は喧嘩に出向いて大変な思いをしましたが、彼女は窃盗を担当しました。今回は逆にしてください。男と女は平等なのですから…。すると女性の部下が反発します。喧嘩のような危険な現場は女性には不向きです。男性を派遣すべきです」
さて、あなたはどう判断しますか?と質問すると、会場のほとんどは迷わず喧嘩には男性警察官を派遣すべきだと答えます。
「火事です。夫は足の不自由な母親を背負い、妻は乳飲み子を抱いて外へ逃げ出しました…が、気がつくと二歳のお姉ちゃんの姿がありません」
さあ、炎の中に飛び込んで子供を助けに行くのは夫か妻か、あなたが好ましいと思う方に手を上げてくださいという質問には、大半の参加者が夫が行くべきだと答えます。
「年頃の娘に恋人ができました。日曜日にはいよいよ相手の両親が正式にご挨拶にいらっしゃることが決まった時、夫が言いました。当日はいつものようにおれがお茶を出すからお前が接待をしてくれよ。おれが台所でお前が掃除。おれたちはずっと得意分野で家事を分担して来たんだからな」
ありのままをお見せしようという夫に従って、あなたは接待を担当しますかという質問には、圧倒的多数が、お茶を運ぶのは妻の方が相応しいと答えます。
さらに、
「今から言うもののイメージを、男性的、女性的、どちらでもない…のいずれかに分けるとしたらどれでしょうか。手を上げて直感で答えてください」
と前置きをして次々と名詞を読み上げて行くと、ライオン、ダンプカー、太鼓、サメ、プロレスラーなどは男性的、カモシカ、スクーター、鈴、金魚、ダンサーなどは女性的なイメージとしてくっきりと分類されます。
「ライオンにはメスもいるのですよ」
「金魚にはオスもいるのですよ」
などと揶揄しながら進めてゆくのですが、男女共同参画社会を目指すリーダーたちの頭の中にも、荒々しく力強いものに対しては男らしさを、可憐で可愛らしいものに対しては女らしさを感じてしまう強固なイメージが存在しているのです。中には頑としてどちらでもないに手を上げ続ける参加者がいて、講師に挑戦的な視線を向けていますが、私は良い悪いを論じているのではありません。一般の中に根強く存在する男らしさ女らしさのイメージが、いかに根源的なものであるかを明らかにして見せているのです。ライオンやダンプカーに男らしさを感じない人は、一般とは随分異なった感性の持ち主であることが証明されただけのことであって、それはそれで構わないのです。ただ冒頭で述べたように、長い間に定着した男らしさ女らしさの観念を意識に働きかけて変革することの困難性については明確になったのではないでしょうか。
行政はトイレの表示を取り上げて、男は青の背広姿、女は赤のスカート姿のシルエットというのは、固定的な男女のイメージに基づいているから不適切であるなどと喧伝し、国の刊行物に紹介される統計資料なども、最近ではわざわざ、男を赤、女を青の棒グラフで表示して混乱を招いたりしていますが、そんなことで一掃できるほど男らしさ女らしさのイメージは表層的なものではありません。胸を開け、腹部をさらし、ひょっとすると臀部まで露出して「女」を強調するファッションが横行する一方で、「女弁護士」という表現は女性の弁護士が例外的であるという印象を与えるから不適切だとか、「女医」という表現も同じ理由で好ましくないだとか、乳児を抱く母親のイラストは、育児は女性の役割であるという観念を助長するから両親揃ったものに変更すべきだなどと、瑣末で教条的な精神運動が行政主導で展開される傾向には違和感があります。大衆は文化にまで強権を発動しようとする行政の姿勢に、戦中の言葉狩りのような印象を受けて、あるところまで来るとしりごみをするのです。
では、なぜ今これほど男女共同参画がかまびすしいのでしょうか。
一つには少子化の結果としての労働力不足があります。女性の労働に期待するしかありません。今一つには経済が成熟しグローバル化した結果としての右肩上がりの成長の終焉があります。人件費を下げて競争力を保ち、少ないパイを分かち合うしかありません。男女雇用機会均等法によって職場が女性に開放されました。育児休業法によって乳児の養育が女性の離職の最大の原因から除外され、雇用主には育児に対する労働条件の配慮が求められました。一歳を過ぎた子供の育児を社会で担うために、保育所の整備を始めとした様々な子育て支援が計画されています。年金も医療保険も、世帯単位から個人単位に変更する方向が模索され、税制は、妻が自分の収入を一定限度以下に抑えようとする動機を排除するために、配偶者控除が見直されようとしています。全ては女性を労働市場に組み入れるための環境整備です。そして、働く女性に家事を中心とした従来の固定的な役割を押し付けないために、男女共同参画が登場したのです。否応はありません。人件費が抑制されるのです。一家のあるじがフルタイムで働けば妻も子も扶養できて、勤続年数に応じて給与が上昇する時代は終わります。つまり夫婦は、子供の養育に社会の力を借りながら、共働きをしなければ生計が維持できない時代がやって来るのです。
考えて見れば少子高齢化とは、若年層より年功を積んだ労働人口の方が多くなるということですから、勤続年数に応じて高い給料を支払う年功序列の給与体系が維持できるわけがありません。現にリストラの憂き目に遭って自殺に追いやられているのは、家族の生計を一身に背負った中高年ではありませんか。年功序列が崩れれば、能力給に移行するしかありません。勤続年数が収入増加に結びつかないとなれば、労働者は能力を発揮できる職場を求めて転職することをためらわなくなり、フリーターや派遣職員が例外的な労働形態ではなくなることでしょう。どうですか?男も女も性別に関係無く能力や個性を発揮して多様な形態で社会に参画する…。男女共同参画社会そのものではありませんか。
夫と対等に働く妻に家事と育児を押し付けるのは不合理です。女性が能力を発揮して管理職に就けば、その下で働く男性にはそういう状況を受け入れる姿勢が求められます。それやこれやについて認識の促進を図るために男女共同参画運動があるのです。
男は仕事、女は家事という相互依存関係がなくなれば、当然離婚は増えるでしょう。幼い頃から社会のシステムの中で養育される子どもの発達についても不安は拭い去れません…が、二つは二つながらここで論ずるにはテーマが巨大すぎます。今回は国が躍起になって促進しようとしている男女共同参画に、経済という側面から光を当てて整理してみたところで紙面が尽きました。
終