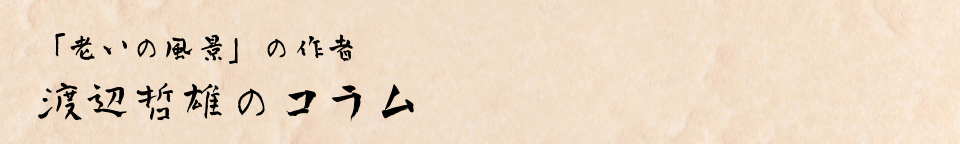- ホーム > 平成16年掲載コラム/目次 > 晴れと褻(け)
晴れと褻(け)
平成16年01月12日
お正月がつまらなくなりました。年を取ったせいだと片付けていましたが、実はもっと別の理由があるのではないかと、この頃しきりに思うのです。
私が子供の頃のお正月は、それを迎えるに当たって、ピーンと張り詰めた緊張があったような気がします。町じゅうに、お正月という名のとてつもなく巨大な生き物がやってくる気配がありました。反対に、暮れの営みは日常そのものでした。新しい年を、やりかけの仕事を抱えたまま迎えたくないために、慌ただしく切りをつけました。前の年の暮れ以来、一度も拭いたことのない場所にも雑巾がけをして、家を丹念に掃除しました。仏壇仏具をピカピカに磨き上げ、正月三が日のご馳走を、おせちを中心に買い整えて、いつもより早めに風呂をつかえば、あとはゆっくりと、ゆく年を惜しむだけです。
やがて除夜の鐘が鳴り渡る中で新しい年が明けると、
「明けましておめでとう」
「明けましておめでとう」
少し他人行儀に、そして他人行儀であることをわずかにはにかみながら挨拶を交わした家族は、一年の計は元旦にありとばかり、松の内をことさら仲良くにこやかに過ごすのです。
「晴れ」と「褻」という言葉があります。
広辞苑で引くと、晴れは「表向き」「正式」「おおやけ」「ひとなか」を指し、褻は逆に「日常」「ふだん」「よそゆきでないこと」を意味しています。元旦は、時間がまるで魔法のように「褻」から「晴れ」に変化して出現した、特別の日だったのです。
今日では毎日が「褻」になりました。いえ、毎日が「晴れ」になったのかも知れません。正月は、大掃除をし、障子を張り替えて迎える特別な日ではなくなりました。おせちは、珍しいものだけを食い散らして生ゴミの袋に捨ててしまう世の中になりました。店は元旦から営業し、町はいつもと同じ喧騒に包まれています。襟を正して一年の計を思う静謐さは、ことさら意識して演出しなければ手に入らない時代になりました。こうしてお正月は、褻から晴れへ変身するすべを失い、日常の延長のつまらない日になったのです。
話は飛躍します。
物体に光を当てれば影ができます。存在は光と影で成立しているのです。人の心も同じように思います。自分の中にある邪悪なものを否定するところに正義が成立し、自分の利益を優先したい衝動を乗り越えるところに愛が成立しています。どこへ出ても小学生のように正論ばかりを言い立てる人物に奥行きを感じないのは、影のない絵画のような平板さを空疎なものと感じてしまうからです。
世の中から晴れと褻の区別が希薄になってゆきます。暮らしぶりだけではありません。教員の犯罪、政治家の汚職、医師の不正、親の子殺し…。本来は世の中の恥として秘すべきことが、知る権利や報道の自由を盾に、連日白日の下にさらされ続けます。報道の制限を主張する立場と受け止められるのは困りますが、その副作用として、お正月が特別の日ではなくなったように、人間の善行にも悪業にも、ひょっとすると戦争に対しても、平面的な情報に接した程度にしか私たちの心が動かなくなってゆくとしたら警戒が必要です。嗅覚が急速に匂いに慣れてしまうように、人間の感受性は、何もかもあからさまな中ではかえって感度を下げる性質を持っているように思うのです。
終