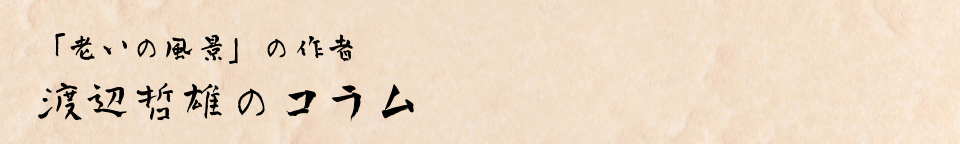- ホーム > 平成16年掲載コラム/目次 > 桜
桜
平成16年04月04日
今年も見事に桜が咲きました。
もしも桜が梅のように、もう少し早い時期に開花する植物だったとしたら、私たちの桜を楽しむ楽しみ方は随分違ったものになったでしょう。人々は早春の寒気の中で満開の樹をただ眺め、本格的な春の訪れを心待ちにしたことでしょう。もしも桜の花が、あのようにはかない命ではなく、咲けば咲いたまま、いつまでも散らない植物たったとしたら、私たちの桜を愛しむ愛しみ方は随分違ったものになったでしょう。開花からわずかの間に人々がこぞって桜のもとに宴を張り、花を愛でつつ親交を深め合うこの国の風習は、ひとえに開花の期間が短いことに起因しているのです。入学、卒業、人事異動…。世の中に数え切れないほどの出会いと別れが錯綜する四月を目前に、桜は人々の切なさを象徴するように一斉に花開き、雪のように散ってみせます。してみると桜は、絶妙な時期と条件を得て、植物以上の存在感を持った幸運な樹木と言わなくてはなりません。
さて、私の通勤コースには、川に沿って延々と桜の公園が続いています。月明かりに濡れる夜桜の妖しい輝きを楽しみながらゆっくりと歩いていた私は、突然聞こえて来た若者の大合唱に思わず立ち止まりました。
「ぼくの名前はヤンボー♪ぼくの名前はマーボー♪」
ふたり合わせてヤンマーだ…という、子供の頃から聴きなれたコマーシャルソングの大合唱でした。若者には宴会の時に唄う歌がないのです。
民謡、軍歌、寮歌、演歌…。農耕民族の血には田植えのリズムが刻まれています。二拍子で両手を打ち鳴らし、みんなで演歌などを合唱すると、民族の持つ「和」の精神が理屈を越えて共鳴するのです。ところが民族は農耕を捨てました。生活様式が変わり、体型が変わりました。世に連れて当然歌も変わり、曲は肉体労働のリズムを忘れました…が、立ってディスコで踊る時はいいのですが、桜の根元にシートを敷いて大地に直接あぐらをかいて見ると、遺伝子の中にかすかに残っている農耕民族の記憶がにわかに目を覚まし、二拍子の歌を恋しがるのではないでしょうか。
ヤンマーでも何でも構いませんが、髪を染めてジーパンを履いた若者たちに民族のリズムを思い出させる力を持っているとしたら、桜はかろうじて大和民族の心根を守る華麗な戦士なのかも知れません。
終