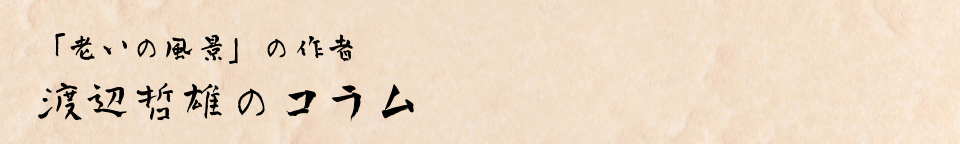- ホーム > 平成24年掲載コラム/目次 > 個人の限界
個人の限界
平成24年03月05日(月)
親しい友人から突然メールが入りました。
『あの人、今夜もいます。この寒さでは死んでしまいます。どうしたらいいのでしょう』
帰宅途中にある小さな町工場の庇の下に毎晩男が寝ているというのです。しっかりと防寒具を着込んでいても歯の根が合わないほど寒いというのに、冷たいコンクリートの階段にネブクロ程度の装備で横たわっていたら間違いなく死んでしまうと、友人は心配しているのでした。自転車を止めてわざわざメールをくれたということは、瀕死の人間を目の前にして、いたたまれない気持ちに駆られたのに違いありません。
『連れて帰ってお風呂に入れて温かいものでも食べさせて、一晩ゆっくりと寝かせてあげたらどうでしょう』
わたしが送った意地悪なメールに、しばらくして友人の悲痛な返事が返って来ました。
『できません、できません。私にはできません』
『そうですよね。私にもできません。個人ではどうにもならないことってあるんですね』
メールのやり取りはそれで終わりましたが、私はその夜、眠れなくなってしまいました。
目を閉じると、自分が庇の下で横たわっているような感覚に襲われるのです。冷たいコンクリート。骨に達するような寒さ。通り過ぎるクルマの音…。懐かしい人や憎い人の顔が脈絡なく浮かんでは消えて行きます。半世紀以上もの長い間、安全な船に乗っているつもりでいましたが、そこそこの地位に着きながらリストラの対象になり、色々あって気が付くと何もかも失って今はコンクリートの上で寝ています。自転車を漕ぐ音が近づいて来てピタッと止まったところで我に返り、私はうつ伏せになって友人のメールを何度も読み返しました。
『あの人、今夜もいます。この寒さでは死んでしまいます。どうしたらいいのでしょう』
『できません、できません。私にはできません』
二つのメールの間に横たわる深い溝を間違いなく私自身も共有しています。
眠れないままに様々な場合を想定してみました。
「助けてください…凍えそうです」
通り過ぎる私に、呻くような男の声が聞こえたとしたらどうでしょう。連れて帰って我が家の風呂を使わせるでしょうか?温かいものを食べさせてベッドに寝かせ、それじゃ気をつけてねと翌朝再び寒空に送り出すのでしょうか?いえ、恐らくそれは無理です。声を聞いた以上、さすがに無視はできないでしょうが、長い間不潔にしたままの見ず知らずの男を、我が家の風呂に入れる勇気はありません。布団を使わせる勇気もありません。
取って返して毛布を差し出したら…とも思いますが、男は工場が始まる時間にはどこかに移動しなければなりません。きっと渡された毛布を持て余してしまうことでしょう。ホテルに泊まるようにと一万円を渡したとしても、おいそれと泊めてくれるホテルはないでしょうし、たとえ宿泊ができたとしても、翌日はコンクリートの上に戻らなくてはなりません。そんなことぐらい百も承知している男は、一万円をアルコールに変えてしまう可能性だってあるのです。
あれこれ考えてみましたが、
「今夜一晩は何とかやり過ごして、明日の朝、市役所の福祉課に行ったらどうですか?何か支援があると思います。あ、体に新聞紙を巻くと随分暖かいようですよ」
自分が決して不親切な人間ではないことを表明するための空疎なメッセージを伝えて、さも心配そうに立ち去るのがせいぜいのような気がします。いっそ男が、「助けて下さい、苦しくて死にそうです」と呻いてくれればことは簡単です。男を乗せた救急車を見送って、私は大変な人助けをしたような気分になることでしょう。
寝ているのが女だったら、年よりだったら、白人だったら、黒人だったら…と色々な状況を想定して見ましたが、可哀そうだと思うことと、実際に自ら手を差し伸べることとの間には埋めることの難しいとても大きな隔たりがあるようです。しかし、同情するだけで何もできないのを偽善と断じることができるでしょうか?凍える男の姿を見て、この寒さでは死んでしまうとメールをくれた友人の文面は、男を心から心配する心情があふれていました。私はそのとき、気の毒な男を何とかできないものかと思う気持ちと、自分の家に連れて帰れないこととは、同列に論じるべきではないように思いました。細胞膜の段階で内部への物質の侵入を峻別する営みが生命活動の原点であるように、個人には、他人が私生活へ侵入することに対する、ほとんど生理的な警戒があるのでしょう。それが他人の人生に関わるときの個人の限界なのです。そいう意味で人間は、仲間が死にかけていても平然と傍らを泳いで行く水槽の中の熱帯魚と変わりません。
一方、人間は社会という連帯のシステムを作って個人の限界を乗り越えました。複数の人から集めた多額な資金と、共通の目的のために人々が協働する仕組みを用いて、個人ではとうてい実現不可能な規模の生産活動を行うようになりました。個人が巨大な生産システムの歯車として機能するようになると、当然のように、わずかなシステムの変更や不具合によって、個人の生活は簡単に破綻するようになりました。生産手段を持たない個人の生活の破綻もまた、個人で対処できる範囲を超えていました。生命体が体内に免疫システムや回復システムを備えているように、社会は、内部における生活破綻の予防と回復のシステムとして、公私にまたがる社会保障体制を構築しました。要するに、タイムラグはあるにせよ、社会は自らの内部で発生する生活破綻については自ら予防救済する自浄装置を装備して運営されるべきなのです。発生する生活破綻の様相は、生産システムの変化に連動しますから、社会保障の内容も生産システムに連動して変化しなければなりません。それが現実には大変困難な課題であるのです。
例えば派遣労働の適用範囲を拡大するという社会システムの変更は、多様な生活スタイルに応じた労働形態の創設といえば聞こえがいいですが、事業主にとっては景気に対応した雇用の柔軟化であり、労働者にとっては雇用の不安定化であり、労働市場全体にとっては正規雇用枠の減少ということになります。
その結果発生する低年収の労働者や、貧富の格差や、失業者の増大に対応する社会保障内容の変更は、温度が上がると作動するサーモスタットのように、一定量の問題が社会的に浮上しないと着手されません。
浮上すべき問題の一つがコンクリートの階段で凍えているのです。心を痛めた友人も、友人からのメールでこの文章を書いている私も、これを読んだ皆さんが示す反応も、浮上すべき問題に参加しています。それやこれやの総和がサーモスタットを作動させるのです。
『あの人、今夜もいます。この寒さでは死んでしまいます。どうしたらいいのでしょう』
気の毒な人を見たら、自分の家に連れ帰れないことを負い目に感じて口をつぐんだりせず、江戸の瓦版屋のように機会ある毎に方々で声高にしゃべりたおすべきだと思うのです。
終