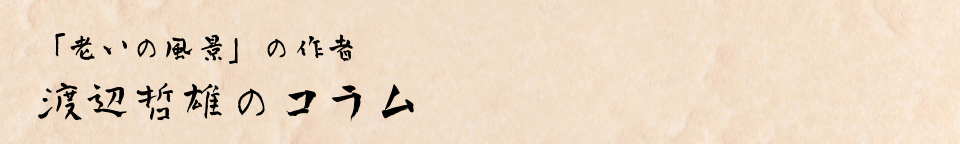- ホーム > 平成24年掲載コラム/目次 > ねむの木は残った
ねむの木は残った
平成24年02月09日(木)
仕事を終えて外へ出たとたん、雪が降る気配がありました。骨に達するような冷気が街をすっぽりと覆っています。一時間余りの道のりを歩いて帰ろうと思っていた私にとって、寒さはいい口実になりました。
(少しだけ体を温めて行こう…)
職場の近くの小料理屋の暖簾をくぐると、
「おや、先生、珍しい」
私と同年代の店主は、カウンターの中で暇そうにしていました。
「こう寒くちゃ歩けないよ。熱いの、一本ね」
私はコートを脱ぎながら、カウンターに並ぶ大皿から里芋の唐揚とれんこんの煮付けを注文し、
「あとは、大根とコンニャクと…あ、玉子ももらおうかな」
通路で湯気を立てているおでんの大鍋を指差しました。
「アジの刺身が値打ちですよ…」
「じゃあ、それももらおうか」
私のほかに客は若い男女が一組だけです。今私が食べなければ、明日にはアジは塩焼きになるのでしょう。
壁のテレビでは、国会中継のダイジェストが流れていました。
「イライラしない?国会中継」
と、ここから先はカウンターをはさんでの店主との無駄話です。
「ものごとが何も決まらないですからねえ」
「外は嵐だというのに、船長以下どっちへ進んだらいいか議論するばかりで船は迷走している。乗客は不安だよ」
「こういうときに国民の心をぐっとつかむ新しいリーダーが出てくると、ガラッと流れが変わりますよ」
「それも怖いよね。宗教もない、理念もない、国家としての背骨は何もない。あるのは経済的関心と責任回避ばかりの国だから」
「その代わり、流れができちゃうと,突っ走っちゃいますからね。オイルショックのときなんか、スーパーからトイレットペーパーがなくなっちゃったでしょ」
「あんときは凄かったよねえ。あれを体験した人も年取っちゃった…」
「考えたら日本は昔からですよ、明治維新も太平洋戦争も、勢いで、だあっとやっちゃった。うまく行けばいいですけど、とんでもない失敗もする。明治んときは国を挙げて廃仏毀釈までやっちゃったんでしょ」
「国宝級の仏像を坊主が風呂の焚きつけにしたんだってね」
「隠岐の島と和歌山県が徹底してたって聞きましたよ」
唐突に廃仏毀釈が話題になるところを見ると、きっと店主は最近その種の本を読んだのに違いありません。
「そういえば隠岐の島は二度行ったけど、立派な神社があったなあ」
「何たって天皇が流された島ですからね」
「島のスナックに案内されたら、最初に出てきたつまみがシイの実だったよ」
「シイの実って、どんぐりみたいな?」
「そう。例の立派な神社で拾ったシイの実をママが炒るんだよ。カリッて歯で鬼皮を割って食べるんだけど、これがなかなか旨くてさあ」
「シイの実って言えば、シイの実学園って施設がありましたよねえ、宮城まり子の。懐かしいなあ宮城まり子。ガード下の靴磨きって歌覚えてます?」
「それって、シイの実じゃなくて、ねむの木学園だろ?」
「ああ、そうそう、ねむの木、ねむの木。ねむの木は残ったって有名な小説がありましたよね。山本周五郎でしたっけ?」
「それはモミの木だよ。モミの木は残った」
「あ、モミでしたか」
カウンターをはさんで二人は笑い転げました。最近こういう失敗が増えちゃって…と情けない顔をして見せる店主と私は同年代です。
「お互いこうやって年取って行くんだよ。どうする?お店。家賃だって大変だろ?」
「いや、それは心配ないんです。自分の店ですから」
「へえっ、こんないい場所が自分のもの!」
「バブルの頃は周りにお店がありませんでしたからね、遠くからもお客さんがわざわざうちへ来てくれました。あの頃、ここ、ビルごと買いましてね、ローンもありません」
「何、それじゃ、住んでるのは?」
「この上の階ですよ」
「だったら老後は安泰だね、うらやましい。店を貸せば家賃が入る」
「貸しませんよ、私ゃ死ぬまで包丁握ります」
と言うときの店主は職人の顔をしていました。
「死ぬまでったって、舌が衰えるんだよ、舌が…。微妙な味がわかんなくなっちゃ板前は終わりだろ?」
すると店主は私の顔を覗き込み、
「だから、同じように味がわかんなくなったトシヨリ相手に料理を出すんですよ」
え?トシヨリってまさかオレのこと?という質問を待たないで、
「いつまでも通って下さいよ、先生」
ダメ押しをされた私はそのとき、ああ、一人で年を取るのではないのだという、不思議な安堵を覚えていたのでした。
終