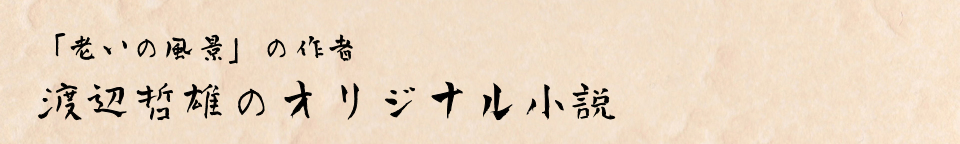- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師22
暴力教師22
ボイスという喫茶店のアンティークなドアには、スイスの牛が首につけているような真鍮のベルが取り付けてあり、客が押し開ける度にそれがガランガランという懐かしい音を立てた。速水憲太郎はベルを鳴らして店に入って来る栗本小枝子の姿を見つけると、奥まった席から伸び上がって大きな手を上げた。
その仕草に、自分が呼ばれたのだと勘違いしたウェイトレスが小枝子の後ろから小走りでやって来た。
「隅っこの席にしたんだ、落ち着くと思って…何にする?」
「私、アメリカン」
「じゃあ僕も。それにしても珍しいな、小枝子の方から電話をくれるなんて。この前のデートを断った罪滅ぼしのつもりかよ」
「何言ってんのよ、いきなりコンサートの券が二枚手に入ったから出で来いったって、こっちにも都合ってものがあるわ。何日か前に誘うのがデートで、その日のうちに呼び出すのは誘拐の手口よ」
「じゃ今日の俺はどうなるんだ。昼間小枝子の電話で、もうこうして呼び出されてる」
「男はいつだって女のために時間を作るの。それが能力と情熱の証しよ」
「勝手なこと言ってる。日本の警察は暇じゃないんだよ」
「はい、十分に承知しております。速水刑事。その優秀な警察に大学の先輩が勤めていて、可愛い後輩の新米記者に色々と情報を提供してくれる。感謝してますわよ。ところでね」
小枝子は今度の毎朝新聞の企画を説明し、
「何かそれらしいネタはない?」
会うごとに刑事らしくなってゆく憲太郎の日焼けした顔を見た。
「学校における暴力ねえ…。面白い事件があるにはあるが、今はいえないよ」
「なぜ?」
「なぜって、さえ子も文屋さんなら公務員の守秘義務ってのは知ってるだろう?こういう話は事故や盗みの情報と違って、色々とプライバシーがからんでるんだ。明日まで待てよ」
「明日って?」
「被害者が正式に告訴すれば、記者クラブ発表だ。明日がその予定になっている」
「記者クラブ発表じゃ、他社の記事にもなるじゃない。スクープにはならないわ」
「スクープってさえ子、お前が取り組んでるのは特集用のレポートなんだろ?」
「スクープになるんなら記事だって欲しいわよ」
「欲張りめ。だけど今度の事件は念入りに取材してレポートするのは賛成だけど、記事にするのは反対だなあ。先生が気の毒だ」
「先生が?」
「どうせ新聞は暴力教師って書き立てるに決まってる」
「それじゃやっぱり先生の生徒に対する暴力なんだ」
「おいおい、それ以上追求するのはよせ。うっかりしゃべってしまいそうだ。ただね、今度の場合、告訴するのは生徒の側じゃなくて先生の側だ。先生が被害者なんだよ」
「ちょっと待ってよ。暴力を振るった先生の方が被害者ってどういうこと?解らないわ。ねえ、速見先輩」
小枝子がいら立ってる。
「まあ落ち着けよ」
憲太郎はそういってポケットからタバコを取り出したが、小枝子が嫌煙権を主張しているのを思い出して引っ込めた。
「世の中には色んなやつがいて、暴力を振るう側が常に悪いとは限らない。そういうことを考えさせてくれる事件だよ、今度のは。先生は今でももちろん被害者だが、本当に被害者になるのは、お前たちが新聞に内容を深く知ろうともせずに、記事の中で殴った先生を暴力教師呼ばわりしてからだろうと思う。だから明日は記者発表をするにはするが、記事にするのは配慮してほしいという異例のお願いがあるはずだ」
「それは変だわ!」
「何が?」
「暴力は暴力よ。理由は関係ないでしょ?そうやってどこかで暴力を容認する姿勢があるから、いつまでもこの種の事件があとを絶たないんじゃない。私、記事にするわよ、絶対に」
「小枝子、お前こそ変だぞ。どうしてそんなに暴力にこだわる。大切なのはそこに至る過程だろうが。例えばだぞ、小枝子が痴漢に襲われる。俺が通りかかった。やめろ!と怒鳴ったくらいでは相手はひるまない。さあ、どうする?俺がそいつをぶちのめそうとするのを小枝子は止めるか?暴力反対って」
「極端な例を出さないでよ。全然状況が違うじゃない。いい?私が問題にしてるのは正当防衛とか緊急避難の場合じゃなくて、権力の弱者に対する暴力なのよ。先生ってのは、生徒にとっては間違いなく権力者なわけでしょ?」
「だけどね、小枝子、先生と生徒がいつだって権力者と弱者という関係で対面するとは限らないだろう。対等な人間同士としてどうしても許せないことだってある」
「どうしても許せなきゃ暴力に訴えてもいいって言うの?それに、先生と生徒はやっぱり対等じゃないわ。いくら人間同士として許せなくったって、生徒はそう簡単に先生を殴れないもの。殴ったら大変よ、非行扱いされちゃって。それが先生だと指導という名の下に許されちゃう。そういう体質を変えていかないと、本当の民主主義は育たないのよ」
「あのね、小枝子」
「もうやめましょう」
「何だ、怒ったのか?」
「怒りゃしないけど解り合えないわ。先輩は男だし、職業だって警察といえばどうしようもなく権力側だし、弱い者の立場は結局解らないのよ」
「小枝子!」
「私、帰るわ。先輩たちのような古くて頑固な常識とペンで闘うつもりよ」
小枝子はぷっとふくれて席を立った。
極端にネコ舌の小枝子のコーヒーは、まだ半分ほど残っている。
「相変わらずだな…」
ようやく嫌煙権から開放された速見憲太郎は、改めてポケットからタバコを取り出した。