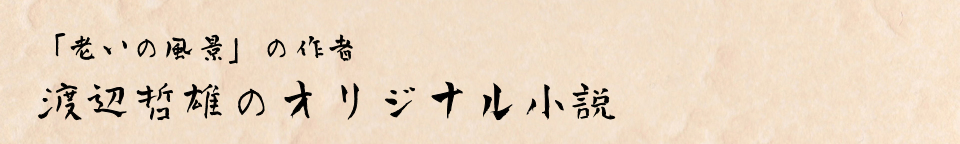- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師16
暴力教師16
浩一は走った。
「浩ちゃん、どこへ行くんだ。おれも行くよ!」
室伏篤久が後を追ったが、浩一はふり切って外へ出た。
「浩ちゃぁん、傘持ってけよお!」
降りしきる雨に臆して、児童用の玄関で立ちすくんだ篤久の声が遠ざかる。
校庭を走り抜けると、浩一の足は靴の中まで泥たらけになった。雨が頭から額を伝わり、鼻の先で次々と飛び散って行く。どこへ行くのか、どうして走るのか、何かから逃げているのか、それとも何かに向かっているのか、浩一には解らなかった。
俊介に殴られたことがひどく意外なようでもあり、ひどく当たり前のようでもあった。
先生、やめて!という四方の声が胸に突き刺さっていた。あの声を聞くまでは確実に浩一が主役だった。しかし、四方が口を利いた瞬間から浩一は見事に脇役に転落した。そのなりゆきがいまいましかった。人々の関心がすっかり四方に移ってしまった教室に、頬を押さえた浩一は、いったいどんな顔をして残っていればよかったというのだ。
「くそ!」
浩一はコーポ北山の階段を駆け上った。こんなときでも結局自分のアパートしか行くところのない現実が惨めだった。ドアを開けると強烈な酒の匂いがした。気まぐれな日雇い仕事に出かけて行く父親の清一は、晴れた日に家にいることだって決して珍しくはなかったが、雨の日は必ず部屋で昼間から酒を飲んでいた。
「千波、お兄ちゃんのジャージ持ってこい!」
「はあい」
言われた通りトレーニングウェアを運んだ千波が、玄関と居間の境のドアを開けっ放しにしたために、
「どうしたんだ浩一、そのなりは」
清一のアルコールでむくんだ顔が、ずぶ濡れの浩一を見た。浩一は初めから父親を嫌っていたが、酒を飲んだ清一はもっと嫌いだった。
「どうしてこんな時間に濡れて帰って来たのかと聞いているだろうが」
という清一の二度目の質問を無視したのがいけなかった。
「このやろう!」
清一がふらりと立ち上がった。
しまった!と思った時は遅かった。
目がつり上がっている。
こうなると手がつけられない。
「親に返事ぐらいしたらどうなんだ!」
清一は力任せに浩一の頬をこぶしで殴りつけた。
千波がわっと泣いて奥へ駆け込んだ。
浩一の左頬は腫れ上がり、見る間に紫色になった。その上をもう一度殴られて、浩一はたまらずに口を開いた。
唇の片端が切れていた。
「先生にやられたんだ」
「先生に?どこを?」
「父さんの殴ったのと同じところだよ」
「あんた騒がしいわねえ、千波が泣いてるわよ」
風呂から上がって来た芳江は、
「まあ、ひどい怪我、どうしたの!」
驚いて浩一の顔を覗き込んだ。
「父さんが…」
という浩一の返事を奪い取るように、
「先生にやられたんだってよ、ひでえ話だ」
清一が吐いて捨てるように言った。
「先生に?」
「そうだな、浩一!」
酔った清一のヘビのような目で睨みつけられると、浩一はそれだけで身体が縮みあがってしまう。
「それにしてもあんた、これはちょっとひどすぎるわよ。浩一が何をしたのかは知らないけど、先生がこんなになるまで生徒を殴るなんて許されないわ。まさか放っておくつもりじゃないわよね?」
芳江に言われるまでもなく、清一は既に上着をはおって車のキーを持ち、
「行くぞ、浩一」
靴を履いている。
「どこへ?」
「黙ってついてくればいい。これから先は、お前は余計なことをしゃべるんじゃねえぞ!」
父と子は、本当に久しぶりに並んで階段を下りた。
雨の中を運転する清一はあせっていた。浩一の頬の腫れが引かないうちに医師の診断書が欲しかった。最初に飛び込んだ県立病院では午後は外科の医師が手術で手が離せないという理由で診断を拒まれた。
「ばかやろう!俺は治療をしてくれと言ってるんじゃねえ。診断書を書いてくれと言ってるんだ。医者なら誰だってそれくらいのことはできるだろうが、この役立たずめ! 」
捨てせりふを吐いて次に回った市民病院でも結果は同じだった。
「専門専門ってえらそうに言うがな、人間の体は一つなんだぞ。何が眼科だ。目ん玉だけ直せるからって、いっちょ前に医者の顔するんじゃねえよ」
結局診断書は、市民病院の看護婦が調べてくれた民間の開業医で手に入れた。口ひげをたくわえた初老の外科医は、手馴れた様子であっけなくペンを走らせた。
『傷病名、打撲傷。殴打によるものと推察され全治二週間と診断する』
清一はその紙切れをさも大切そうに上着のポケットにしまいこんだ。