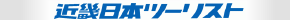護徳寺 Gotokuji Temple 阿賀町
| 日出谷駅に下車、阿賀野川に沿う国道459号を2キロほど行くと、その道筋の中村集落に真言宗護徳寺がある。 護徳寺は、会津領主芦名氏が、その念持仏を祭って創建したと伝えられる。永生9年(1512)、尊栄師によって開かれた。小川庄三十三霊場の一番札所でもある。 寺域は約3400平方メートル、木々に囲まれて本堂・庫裏・観音堂などがある。本堂の脇に「雨乞いの池」と呼ばれる小さな池があり、日照りの際、池の水をかき混ぜると雨が降ったという。 観音堂護徳寺の参道に入ると杉木立を背にした茅葺き屋根の簡素なたたずまいを見せる観音堂が姿をあらわす。お堂は桁行・梁間とも三間四方の小堂となっているが、組み物など手法は雄大で室町時代の特色をよく表し、会津と越後の中世建築のつながりを知る上で貴重なものとなっている。観音堂の建立は、弘治3年(1557)。昭和41年(1966)から14か月をかけておこなわれた解体修理で、建立時にしか書き込むことのできない天井の一角に墨書が発見され、その年代が明らかになった。 堂内に入ると、柱や壁板には、戦国時代から江戸初期にかけ、武士や商人などが本堂を一夜の宿とし、その徒然に書き残した落書きがびっしりと書きしるされ、会津と越後を結ぶ街道のにぎわいが伝わってくる。 堂内正面にあるのは、固く閉じられた扉。その奧の厨子(ずし)の中には、秘仏である聖観音像が鎮座している。鎌倉時代から会津地方を支配していた芦名一族が伊達氏との抗争の際、ひそかにここへ持ってきたといわれる。秘仏は鷹さ187㎝、全身に彩色が施されている。 観音堂は、室町時代の建築様式を残し、会津地方と越後地方との中世建築の関連を知る上での貴重な史料となっており、昭和36年(1961)に県の文化財に、昭和38年(1963)に国の重要文化財(建造物)に指定された。 ≪現地案内看板≫
国指定重要文化財(昭和38年7月1日指定) 護徳寺観音堂一棟  この観音堂は桁行三間、梁間三間、一重寄棟造の小堂で弘治3年(1557)に建立された。 この観音堂は桁行三間、梁間三間、一重寄棟造の小堂で弘治3年(1557)に建立された。堂の由緒は、中世会津地方に天正17年(1589)に滅亡した葦名氏が伊達氏との抗争に際し、念持仏(聖観世音菩薩)をひそかに移したところと伝えられている。 その後の沿革については明らかでないが、この地方一円は、江戸末期まで会津領下であって、寛政5年(1793)の覚書によれば、領主松平氏から年々修復料を受けて維持修理してきたことが明らかである。 また、記録に残る修理としては、宝暦3年(1753)天明5年(1785)文化5年(1808)に屋根の葺替を、寛政10年(1798)には向拝や縁廻りの改造、大正6年(1917)には茅葺き屋根を桟瓦葺に葺替えている。 建物は、全体的に唐様形式からなり、会津越後両地方の中世建築の関連を知る上で重要な遺構として昭和38年7月1日重要文化財に指定された。昭和41年10月より昭和42年11月まで総工費890萬円をもって解体修理が施工され、ほぼ創建当初の姿に復元された。 堂の全面から背面までかけ渡した大虹梁やこれに四個の大瓶束をすえて斗栱を支えている形式は、県内は勿論会津地方にも他に例を見ない独特の手法として注目されている。 阿賀町教育委員会 |
|
|