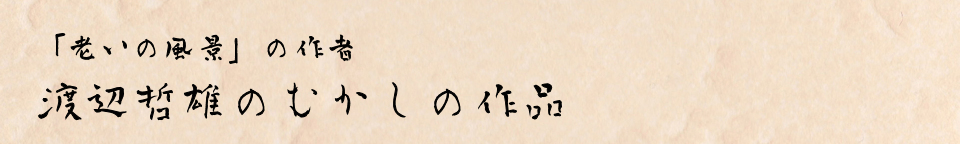忠犬八公とミケ
作成時期不明
あわただしい一日でした。黒い服を来た大勢の人たちがやって来ては帰って行き、それがご主人のお葬式であることを知った今でも八公はご主人の死を信じることができません。いつものように駅で待ってさえいれば、ご主人が手を振りながら元気に改札口から出てくるような気がします。
八公は駅へ出かけて行きました。
ご主人を好きであることをやめようとしていたことなどすっかり忘れてしまい、次の日もそのまた次の日も八公は駅へ出かけて行きました。
電車が着くたびに改札口から吐き出される人々の群れの中にご主人の姿を探す八公の瞳は、その都度希望の光を失って行きました。待てど暮らせどご主人の姿を見つけることができないまま、いったい何日が過ぎたでしょう。
冬の駅前広場の片隅で今日も八公はしょんぼりと座っています。どんなに座りつづけても二度と現れることのないご主人を待ちながら、八公は泣いていました。
(ご主人に会いたい…ご主人に会いたい…)
ひざに抱いてもらえなくても、部屋に入れてもらえなくても、そんなことは今の八公にとってどうでもいいことでした。大好きなご主人にひと目会いたいという気持ちだけが八公の心の中で燃え残っていました。いいえ燃え残っているというよりは、ご主人に会うことができなくなった今、初めて鮮やかに燃え上がったといった方がいいでしょう。
「ボクはご主人のことが好きだ!誰が何と言ってもご主人のことが好きなんだ!たとえこのまま永久に会えなかったとしても、ボクはずっとこうしてご主人のことを待ち続けるぞ!」
八公は決心しました。確かにミケの言う通り、心を縛られたまま生活するのは窮屈で不自由な暮らしかも知れません。しかし、この世で一番大切なものを失った哀しみを、そう決心することでしか八公にはどうしても乗り越えることができなかったのです。
* * * * *
東京の渋谷の駅前に八公の銅像が立っています。
帰らぬご主人を十年間も待ち続けて死んだ忠犬として、凛々しい顔を大空に向けています。その銅像が完成した時は、黒山の人だかりができるほどの評判だったということですが、大勢の見物の人たちに混じって、まぶしそうに八公の銅像を見上げている一匹の年老いたネコの姿があったことに気がついた者はありませんでした。それがミケでした。そして、その時のミケが、銅像になってまでもまだご主人を待ちつづけている八公の姿を眺めていったい何を思ったのか、残念ながらそれは知るすべもないのです。
終