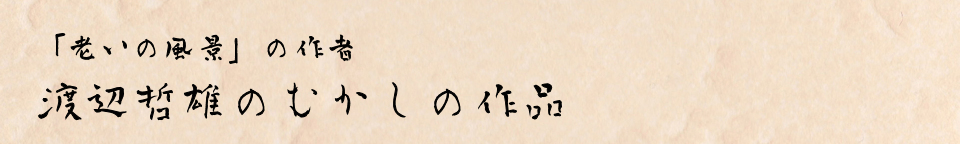檻の中のごん太
平成29年10月24日(火)掲載
ポン吉はわざと冷たく言いました。人間を好きになってどうなるというのでしょう。こんな窮屈な檻の中で、一生を過ごさなくてはならないのは、みんな人間のせいではありませんか。
「悪いことは言わないよ。早いとこ忘れてしまうんだ。きみがいくら人間を好きでも、人間の方はきみが思うほどきみのことを好きじゃないんだよ」
「うそだ!うそだよ」
ごん太は言いました。
「みんなぼくを見にわざわざやって来るんだ。そしてたくさんのお菓子を投げてくれる。人間がぼくのことを好きだという何よりの証拠じゃないか」
「それはきみが檻に入っているからさ。檻に入っていて安全だと思うから、人は安全な分だけ心を許すんだ。きみにはそれが分からないのかい?」
どんなにポン吉が説得してもむだでした。人気者のごん太にはポン吉の言うことがどうしても分かりません。人間たちとすっかり友だち気取りのごん太は、ポン吉の言うことには耳を貸そうともしないのです。そんなある日、ごん太はポン吉に、檻を抜け出す手助けをして欲しいと言い出したのでした。
「本気でそんなこと考えているの?」
ポン吉が驚いて尋ねると、ごん太は真剣な顔でうなずきました。こっそり檻を抜け出して女の子を探しに行くと言うのです。ほとんど毎日のように動物広場に遊びに来ていたということは、女の子は広場の近くに住んでいるに違いありません。匂いを頼りに歩き回れば、探し出せないことはないでしょう。
「もしもあの子が病気でもしていたら、ぼくは知っているだけの芸を見せて喜ばせてあげるんだ」
ごん太は思いつめていました。
「止めてもむだだね」
ポン吉は言いました。
動物園で生まれて、ずっと檻の中で育ったごん太には、檻の外の自由も分からない代わり、その怖ろしさも決して分かりはしないのです。ポン吉はごん太が可哀想になりました。一目だけでも女の子に会わせてあげたいと思ったのです。
「わかった。協力するよ」
そう答えたことを、あとでどんなに後悔することになるのか、そのときのポン吉には想像することもできなかったのです。
コツ…コツ…と靴音が響きます。飼育係りのおじさんが餌を運んできたのです。ガチャン!と鍵を開ける音がして、重い鉄の扉がギーッときしみながら開きました。ちょこんと正座したごん太が、とびきり丁寧に頭を下げると、飼育係りのおじさんは餌の入ったバケツを床に置いて言いました。
「相変わらず可愛いやつだなあ、この檻に来るのが一番の楽しみだよ」
…と、そのときです。
隣りの檻のポン吉が突然苦しみ始めました。
「痛いよ」、「痛いよ」。
ポン吉はおなかを押さえて檻の中を転げまわります。
「どうした、ポン吉、大丈夫か?」
飼育係りのおじさんは、思わずポン吉の檻に駆け寄りました。
ごん太の檻の扉は開いたままです。
一瞬の隙を突いて、真っ黒なかたまりが風の様におじさんの後ろを通り抜けました。
「大変だ!ごん太が、ごん太が逃げたぞ!」
飼育係りのおじさんの大声が夕暮れの広場に響き渡りました。
「うまくやれよ…」
出口に向かってまっしぐらに駆けて行くごん太の黒い背中を、ポン吉は祈るような気持ちで見送りました。
それがポン吉がごん太を見た最後の姿になったのです。
くんくんと匂いを嗅ぎながら、夜の町をごん太が歩き回ります。真っ黒な体は闇夜に溶けて、まるで二つの目玉と首の白い月の輪だけが歩いているように見えました。初めての町は思ったより広く、それに余りにたくさんの人間たちの匂いが混じっているために、たった一人の女の子の匂いを嗅ぎ分けるのは容易なことではありません。それでも、ごん太は歩きました。手当たり次第に、とにかく歩いてみるより仕方がないのです。
街角を曲がったところで最初の人間たちに出会いました。
「こんばんは!」
驚かしてはいけないと思い、ごん太はできるだけ愛想よくおじぎをしましたが、返って来たのは、キャーッ!という悲鳴でした。
「怖がらなくてもいいよ。ほら、ぼくだよ、ごん太だよ」
ごん太が追いかけようとすると、飛んで来た靴が、ごん太の鼻先に当たりました。
「じゃ、逆立ちして見せてあげるよ。ごん太だという何よりの証拠さ、ね、うまくできたら怖がるのをやめて」
鼻の痛みを我慢して、よいしょと得意の逆立ちをして見せたごん太が、
「分かっただろ?」