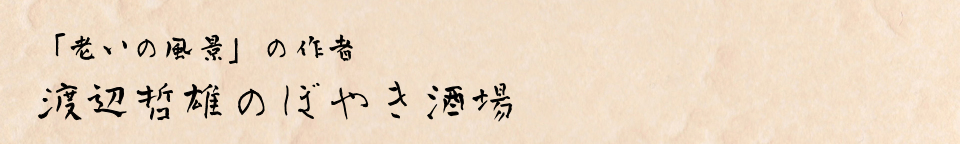スマホ
令和元年12月20日
もう一軒行こうと足を延ばした路地に、その居酒屋は赤い提灯をぶら下げていた。
「ぼやき酒場?」
提灯には黒々と、紺の暖簾には白い染め抜きで、大きく『ぼやき酒場』と書いてある。
「おい、ぼやき酒場だって。面白そうじゃないか」
「入るか」
「入ろ、入ろ」
利明と隆成が引き戸を開けると、十二人で満席のコの字形のカウンターの中で、
「へ、らっしゃい!」
刈り上げの頭に手拭いを巻いた六十代と思しき作務衣の主人が、鼻先にひっかけた眼鏡の上から二人を見た。
「お客さん、済みません、一つズレて頂けますか?」
主人が空けてくれた二つの席に並んで座り、利明と隆成は壁のメニューを見た。手作りの一品料理の短冊がずらりと貼られ、目の前でおでんの鍋が湯気を上げている。
「大将、熱燗で二合。あ、お猪口は二つね。それから、とりあえず、おでんを適当に見繕ってよ」
「あいよ」
「ところで、あそこに貼ってある本日のぼやきメニューって何ですか?スマホって書いてあるけど…」
利明の質問には答えないで、主人はコンロの鍋の湯に二合徳利をタポリと沈め、おでんを手際よく皿に盛りながらにやにやと笑っている。
「あれはですね、最近のスマホ社会について我々が自由にぼやくんですよ、腹が立つことあるでしょ?スマホって」
代わりに隣のサラリーマン風の男が答えた。
「スマホについてだけですか?」
という隆成の質問には、
「そう…大将が決めた本日のテーマはスマホ。テーマは日替わりですからね。もちろん、スマホから発展した話題なら何でもOKです」
別の客が答えた。
すると、満席の客がわれ先と話し始めた。ほとんどが四十代以上の男ばかりである。
「テーマがあるとぼやき易いんですよ。ぼやきは他の客に聞こえたって構いません。いや、聞こえた方が盛り上がります。静かに飲みたい客は出て行きます」
「そう…。出て行っても、ぼやきたくなるとやって来ます」
「へい、熱燗とおでんお待ち」
二人の前に主人の手が伸びて注文の品をカウンターに置いた。
「セクハラだ、パワハラだ、個人情報だ、プライバシーだって、何をしゃべっても差し障る世の中ですからね。それでお互いを窮屈にしてる。みんな風通しが悪いと思っているんだけど、結局、批難に怯えて言いたいことも言えないでストレス溜めてる。ここなら知らない者同士、自由にぼやいて恨みっこなしです。自分のぼやきを聴いてもらえれば、すうっとするし、人のぼやきが自分と同じだったりすると、ああ、おれだけじゃないんだと、これまた気持ちが楽になる」
「要するにストレス解消酒場ですよ、ここは」
「話が途切れると、大将が上手に話題を振るんです。ああ見えて大将は昔、NHKで働いていたんですからね」
「すごい!アナウンサーですか、NHKで!」
隆成が驚くと、
「はは、新潟北部観光という旅行会社ですよ、それでNHK」
言った本人が笑い転げ、周りの客と一緒に主人までが初めて聞いたように噴き出したところを見ると、旅行会社そのものが冗談らしい。