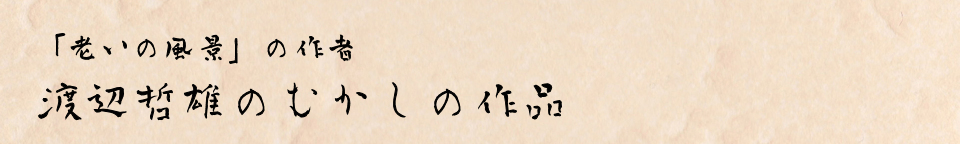魔法の消しゴム
作成時期不明
真夜中です。
机に向かったトンガリ王子は一枚の紙切れを前に、深刻な顔をして鉛筆を握っています。魔女は、王子にもらった新しいほうきに乗って大喜びで帰って行きました。そして、王子の手元には、ほうきと引き換えに手に入れた魔法の消しゴムが一つ残っているのです。
「三つだけ…」
と魔女は言いました。いくら魔法の消しゴムを使っても、人間が消すことのできるものは三つだけだと言うのです。
「三つだけか…」
王子の心は決まっていました。
『ゴミ、病気、犯罪』
白い紙に三つの文字を書いた王子は、魔法の消しゴムを使ってそれを丹念に消しました。
(この三つがなくなれば、トンガリ王国は見違えるほど住み良い国になる)
王子はベッドに横になって目を閉じました。汚らしい服を着た掃除夫や、パンに群がる子どもたちの姿が浮かんで来ます。しかし、それも今夜限りです。明日になれば、それぞれに明るい顔をして新しい生活を始めることでしょう。
いつの間にか安らかな寝息をたてて眠りに落ちたトンガリ王子には、今夜の結果がいったいどんな思いがけない形で現れることになるのか、想像することもできなかったのです。
『入院患者ぞくぞく退院!』
という明るいニュースが新聞の一番最初に大きな見出しで取り上げられたのは、それから二日目のよく晴れた日のことでした。
「大臣、すがすがしい朝だ。ちょうど私の心のように晴れ晴れとしておるではないか」
王子は大変なご機嫌でした。なにしろ自分の力で大勢の不幸な人々を救ったのです。そう思えば王子の顔に知らず知らずほほえみが浮かぶのは無理のないことでした。
「これで驚いてはいけないぞ。わが国は今日を境に良いことが毎日のように続くのだ」
ところがそんな王子の期待とは裏腹に、次の日の新聞の記事は、決して明るいものではありませんでした。
『退院患者に仕事を!』
『病院、次々に倒産』
いいえ、それだけではありません。空っぽになった病院では医者も看護師も仕事を失い、将来、医者や看護師を目指して一生懸命勉強に励んでいた若者たちは、目標を失いました。実際それは大変な出来事でした。「放ってはおけぬ」ということで、宮殿では早急に会議が開かれました。「彼らは困っております」町の様子を調査して来た家臣の一人が報告しました。「町は仕事を求める者であふれております。このまま行けば、やがて彼らは飢えてしまうでしょう。そのくせ彼らはどういうわけか盗みを働いたり人の物を奪ったりはしないのです」「盗みといえば…」別の家臣が言いました。「不思議なことに毎日町のどこかで必ず起きていた犯罪が、このところピタリと影をひそめました。警察官はすることもなく無駄に一日を送っています。この状態が続けば警察官のほとんどは雇っておく訳にはいかなくなるでしょう」「首を切らねばならぬのは警察官だけではありません。お気づきのこととは思いますが、町にはゴミというゴミが姿を消しました。掃除夫だとて同様に、いつまでも遊ばせておくことはできませんぞ」「いったい、いったい何が起こったというのだ!」次から次に報告される町の様子を聞いた王様は、すっかり頭を抱え込んでしまいました。しかし、本当に頭を抱え込んだのは、トンガリ王子の方でした。「わ、私は間違ったことをした覚えはないぞ」王子は真っ青な顔をしてそうつぶやきました。その時です。
「我々に仕事を!」「我々に目標を!」宮殿の外で、大勢の人間の叫び声が聞こえて来ました。「大変です、仕事を求める国民が宮殿へ押し寄せて参ります!」王子は立ち上がりました。もうあれこれ考えている暇はありませんでした。このまま放っておけばトンガリ王国はつぶれてしまいます。王子はあわてて自分の部屋に戻ると、机の引き出しから魔法の消しゴムを取り出しました。「消したものを元にもどしたければ、魔法の消しゴムを消してください」あの魔女は確かにそういいました。『魔法の消しゴム』王子は震える手で紙切れにそう書くと、旨が張り裂けそうないきどおりをこめて、その文字を消しました。「なぜだ、どうしてだ、ゴミも病気も犯罪も、わが国にはいらないものばかりのはずだ。私は必要のないものを取り除いてやっただけのことではないのか!それなのに、どこが、どこが間違っていたというのだ!」歯ぎしりをして悔しがる王子の手から、まるで嘘のように消しゴムが消えて、代わりに王子の胸に言いようの無い哀しみが生まれました。トンガリ王国は何もかもすっかり元の状態に戻りました。町にはゴミがあふれ、朝から晩まで真っ黒になって働く掃除夫の姿がありました。医者は大勢の患者と取り組み、警察官は毎日のように泥棒を追いかけて走り回りました。何年か経ちました。トンガリ王子はふと、あれは夢ではなかったのかと思うことがありました。しかし世の中は大きな大きな生き物で、いっぺんに変えようとすれば死んでしまうという王様の言葉だけは、決して忘れることがありませんでした。
終