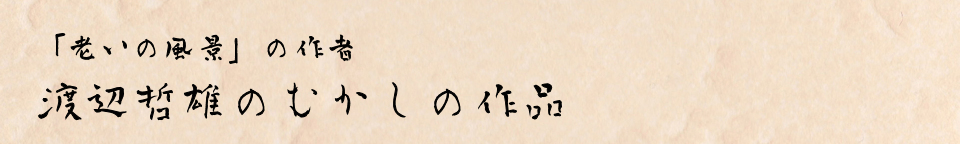ぽん吉の恋
平成29年11月09日(木)掲載
杉の木峠に住むたくさんのたぬきの中で、誰が一番化けるのが下手かといえば、それはもうぽん吉に決まっていました。
あるときお地蔵さんに化けたつもりのぽん吉がすまして道端に立っていると、通りすがりの村人が言いました。
「たぬきかきつねか知らねえが、お地蔵さんに化けるときにゃ、ちゃんとひげを隠すもんだ」
村人に嫌というほど引っ張られたひげが痛くて痛くて、ぽん吉は泣きながら一目散に峠へ逃げ帰ったものでした。
またあるときは、小判に化けたつもりのぽん吉が道に寝そべっていると、驚くはずの村人は、
「汚えわらじが落ちてるだ」
と、力一杯踏んづけて行きました。このときもぽん吉は、はらわたが飛び出してしまうかと思うくらい痛い思いをしたものです。
苦心して化けた石灯篭には太い尻尾がついていましたし、ぽん吉が化けた蛇は、どこから見てもただの縄でした。
仲間たちから、ぶきっちょぽん吉とあだ名を付けられて、
「おら、ほんとにだめなたぬきだ」
としょげ返るポン吉を、いつもやさしく慰めるのは幼なじみのぽん子の役割でした。
「化けるの下手でもいいでねえか、私、そういうぽん吉さんが大好きなんよ」
けれど、ぽん吉には夢がありました。一生懸命練習をして、峠で一番の化かし上手になるのです。そして、ぽん吉のことを馬鹿にした仲間たちを見返してやるのです。化けることさえ上手くなれば、ぽん子よりうんときれいなお嫁さんだって見つかるかも知れません。
「何とかして上手く化けられるようになれないものか…」
明けても暮れてもそのことばかり考えているぽん吉が、ある日、ふと思いついたのは、ぽん太郎じいさんのことでした。ぽん太郎じいさんは、若い頃には化かし名人とまで言われたたぬきですが、今ではすっかり年老いて、峠の洞穴でひっそりと暮らしていると聞いています。ぽん太郎じいさんに相談すれば、きっと何か良い知恵を貸してくれるかも知れません。ぽん吉はじいさんの喜びそうな手土産を持って、わらをもすがるような思いで洞穴に出かけて行きました。
「こんにちは」
「ごめんくだせえ」
洞穴の入り口から聞こえる大声に、せっかくの昼寝を起こされたぽん太郎じいさんが、眠気まなこをこすりながら外へ出てみると、若者のたぬきが立っています。その思いつめたような瞳を見たとき、ぽん太郎じいさんには、ぽん吉の用事が何なのか見当が付きました。
以前にも同じような瞳をした若者が訪ねて来たことがありました。
「化かし名人になりてえ!」
と言うその若者を、ぽん太郎じいさんは怒鳴りつけて追い返したものでした。化けるのが上手いからって、それが何になるんだとぽん太郎じいさんは思うのです。確かにぽん太郎じいさんは、若い頃は化かし名人ともてはやされたたぬきでした。けれど年を取って体が衰えるにつれて、化けるのも下手になって行きました。やがてぽん太郎じいさんが、もう上手く化けられないと分かると、それまでちやほやしてくれた仲間たちは、みんないつの間にか離れて行きました。気づいたときには、地位も名声も友達も残ってはいませんでした。淋しくて、つらくて、毎晩酒を飲んでは荒れるようになったぽん太郎じいさんに愛想を尽かして、あんなに仲が良かった女房までが、子どもを連れて出て行ってしまったのです。名人と言われていい気になっていた罰が当たったのだと思いました。こんなことなら、たとえ化けるのは下手でも、真面目に働いて、有名でも何でもない本当の自分を心から好きになってくれる者を嫁にすればよかったと後悔しました。一人ぽっちの自分を振り返ってみると、これからの若者には決して自分と同じ道を歩かせてはならないと思いました。帰れ!と若者を追い返したのは、じいさんの精一杯の親切だったのです。
ところが、さすがのぽん太郎じいさんも、ぽん吉の強情には手を焼きました。怒鳴っても、なだめても、すかしても、
「化け方を教えてもらうまで、おら、ここを動かねえだ!」
洞穴の入り口に座り込んだまま、ぽん吉はてこでも動きそうにありません。この調子では、ぽん吉は、二日でも三日でもこうして座っているつもりです。