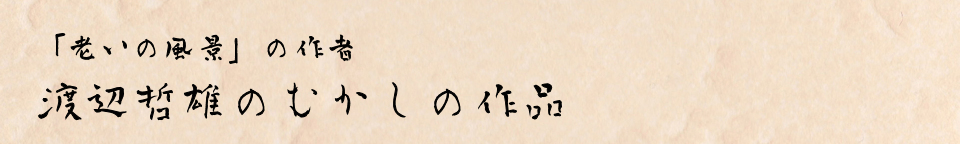エドワード夫人の散歩
作成時期不明
劣等感…。それは何とやっかいなものなのでしょう。
(私は醜く太っている)
という想いが、何不自由ない大金持ちのエドワード夫人の心に、まるで接着剤のようにくっついたまま離れません。しかもさらに困ったことには、自分が劣等感を抱いているということを他人に見透かされるくらいなら醜い体を裸で人前にさらした方がまだましだと思うほど、それは密やかな感情であるということでした。痩せるためには体を動かさなくてはならないことは解っています。しかし、マラソンはもちろんのこと、美容体操のための器具も買い入れるわけには行きません。そんなことをして、痩せたい…というエドワード夫人の願いがもしも町の連中に気づかれでもしたら、ささやかれるうわさは決まっています。
「ブタはどんなに走ってもカモシカにはなれないだろうよ」
「それに、あの可哀想な自転車は、婦人が痩せるより先につぶれてしまうに違いない」
エドワード夫人の努力が真剣であればあるほど、うわさは益々残酷になってゆくはずです。庶民にとってはいつだって、金持ちを笑いのネタにするほど愉快なことはないのです。エドワード夫人は考えました。寝ても覚めても考えました、考えて考えて、さんざん考え抜いたあげくに思いついたのが、犬の散歩だったというわけです。
普通の家庭なら、家族四人が楽に三ヶ月は食べてゆけるほどの大金を支払って、血統書付きの立派なシェパードが選ばれました。さすがに高価な犬だけあって、鼻筋が通り、耳と尻尾がピンと空を向いて、金の首輪をはめると金持ちの犬にふさわしい気品が漂いました。銀の鎖と絹のパラソルを手に、さっそく夫人の散歩が始まりました。夫人の散歩といっても、表向きは夫人はあくまでも犬を散歩させているのであって、自分の美容のために運動をしているのではありません。エドワード夫人の計画は成功しました。お金持ちらしく優雅に、そしてたっぷりと時間をかけたエドワード夫人の散歩は、またたくまにすっかり有名になりましたが。人々の関心はもっぱら婦人が連れているシェパードの方に向けられました。
「素晴らしい犬だ」
「あれほどの犬は見たことがない」
というささやきが聞こえてくる度に、エドワード夫人は満ち足りた気持になりました。
誰も自分の劣等感に気がつくものはいないという安心感が婦人の行動を大胆にするのでしょうか。雨でも降らない限りパラソルを替えドレスを替えて、エドワード夫人の散歩は次第に華やかなものになって行ったのです。
* * * * *
夫人は劣等感から解放されました。いえ、開放されたというよりは、目をつぶることにしたといった方がいいでしょう。体は一向に痩せる気配はありません。それどころか適度な運動で食事が進み、以前よりも少し太ったような気がします。それでもあの血統書付きのシェパードを連れて町を散歩する限り、人々はうらやましそうにため息をつくことが分かると、夫人はもうくよくよしてはいられませんでした。全身鏡を取り外し体重計を片付けて、エドワード夫人はつぶやきました。
「太っていることを気にするのはもうやめにするわ…。そんなことを引け目に感じなくても、私は今、誰からもうらやましがられる素晴らしい犬の飼い主なんだもの」
こうして夫人は心の中でたくみに劣等感を優越感とすり替えることに成功したのです。
犬のための美容師が雇われました。犬のための調理師も雇われました。首輪も金の首輪の他に銀の首輪と宝石をちりばめた鹿皮の首輪が用意されました。ごちそうを食べて艶の良くなった毛にたんねんにブラシをかけ、目の覚めるような首輪をつけると、シェパードはまるで犬の王様のようになりました。そのシェパードの後ろから、これまた女王様のように着飾ったエドワード夫人が歩きます。私の犬は世界一だわ…という自信が微笑みとなってエドワード夫人の顔にあふれていました。生きがい…というと大袈裟かもしれませんが、町で出会う人々の表情の中に驚きとあこがれと、そしてうらやましさを発見する度に、夫人は幸福な気持になりました。
「夫人の犬は見かけ倒しの負け犬だ」
といううわささえ聞こえて来なければ、エドワード夫人の心はそれからもずっと、秋の空のように晴れやかでいられたに違いありません。
「負け犬?」