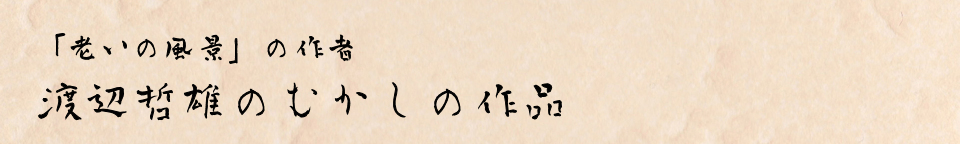哀しみのお姫様
平成29年12月25日(月)掲載
ちょうど同じ頃、見知らぬおじさんの家に連れて行かれた人形の方でも、かおりちゃんに負けないくらい悲しい思いをしていました。
「ねえ、お願い、私を帰して…私はかおりちゃんと一緒に暮らすつもりでいたのよ。いいえ、一緒に暮らすのは無理でもウィンドウの中でただ見つめられているだけで幸せだったの。それにいつものようにおもちゃ屋さんへやって来たかおりちゃんが、私がいないことを知ったら、いったいどんなに悲しむか…。ああ、まるで目に浮かぶようだわ。ねえ、お願い。私を帰してよ、おじさん」
小さな箱の中で一生懸命お願いする人形の声は、おじさんの耳には届きません。
「おじさん、聞いてよ。ねえ、おじさんたら!」
人形は大声で呼びかけました。呼んで呼んで呼び疲れ、そして人形はあきらめました。考えて見ればウィンドウに飾られた人形には、お客さんを選ぶ自由など初めからありません。誰が買おうと勝手ですし、誰に買われようとそれが人形の運命なのです。売れ残ってお店の厄介者になるかも知れないつらさを考えれば、買ってもらえただけでも幸せだと考えなくてはなりません。思い直した人形の周りでカチャカチャと食器の触れ合う音がして、どうやらこれから誕生日のお祝いが始まるようでした。人形は真っ暗な箱の中でじっと耳を澄ませました。
「さあ、ミチル、お姉ちゃんにおめでとうを言おう」
「誕生日おめでとう!」
「おめでとう!」
「それじゃルミ、ろうそくの火を消して」
お母さんに言われて、ルミちゃんがバースデーケーキのろうそくを勢いよく吹き消したのでしょう。パチパチと拍手の音が聞こえます。
「はい、ルミ、これはパパからのプレゼントだ」
とお父さんが言い、ルミちゃんが包みを開けるまでのほんの短い時間に、人形の胸は不安と期待で張り裂けそうになりました。誰だって初めての人に出会うのは楽しみだったり心配だったりするものです。ましてや人間に可愛がられるためにこの世に生まれて来た人形にとってはなおさらのことでした。
「いったいどんな人たちだろうか…」
「ルミちゃんも、かおりちゃんと同じように私のことやさしいまなざしで見つめてくれるだろうか…」
「もしも…もしも気に入られなかったらどうしよう…」
あれこれとめまぐるしく想像を巡らす人形の瞳に、まぶしい電燈の光が飛び込んで、人形はようやく窮屈な箱の中から取り出されたのです。