青梅ナビ
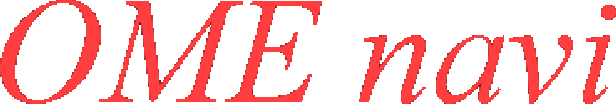
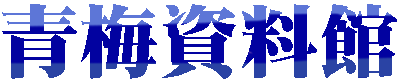
青渭神社のいわれ
新編武蔵風土記稿(ムサシフウドキコウ)には、このようなことが書かれている。
平将門(タイラノマサカド)が反乱をおこしたとき、鎮守府将軍(チンジュフショウグン)の源経基(ミナモトノツネモト)が追悼のため、このあたりにきた。 そのとき多摩川の水が急に青く変わったので、「これは奇妙なことがあるものだ。」 と思った。 しばらく、そこにたたずんで眺めていると、神社の方からひとりの童女があらわれた。 童女は、将軍に向かってこういった。
「東国の反乱を追悼する霊神(レイジン)が、あなたを守っておりますので、かならずこの戦(イクサ)に勝つでしょう。
将軍は、このことばに勇気を得て、ついに将門を討つことができた。
当時、この神社には、まだきまった社号がなかったので、川水のめでたいしるしに因(チナ)んで青渭神社とした。
だが、これは歴史的に見て、信じられない。
式内神社孝(シキナイジンジャコウ)には、青渭の神社は、沢井村にありと書かれている。 渭の字は、ヌマとも読み、「青沼」というのかもしれない。 土地の人は、青波、ともいう。 深大寺にも、青波天神というのがあり、これも青渭の神社で前に池がある。青渭神社 したがって、青波といういわれは、社の前に池があり青い波があてりにただよっているので、いつとはなしに、こういう字に書かれたのかもしれない。
いずれも、明確なものではない。
と、している。