青梅ナビ

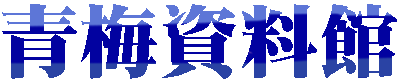
権左淵のカッパ
むかし、多摩川に権左淵という大きな淵があった。
ここは、権左という人が身を投げたことからこの名がついたという。
権左淵は深く、いつも青黒いうずを巻いていた。 淵には、たくさんの魚がいて、村の漁師の大切な魚場でもあった。
ところが不思議なことに、いつのことからかぷっつりと魚が捕れなくなってしまった。
ある秋の夕暮れ、三田の殿様の馬丁(ばてい)が、この淵で馬を洗ってやって厩(うまや)に帰って行った。
その後、いつもは夜中にかいば桶をガタガタいわせる馬が、コトリとも音をさせない。
変だなとは思ったが、馬丁はそのまま眠ってしまった。
あくる朝早く、馬丁が厩にいってみると、かいば桶がすみの方にひっくりかえっていた。
桶をもちあげてみると、中に妙なものがうずくまっているではないか。 それは、赤ん坊ほどの大きさで、蛙(かえる)の化け物みたいな生き物であった。
「やい。 なんだお前は。」
馬丁は、ムチをふりあげて生き物をにらみつけた。
「い、命ばかりはお助けを。 わっしは、拝島(はいじま)の竜ガ淵(りゅうがぶち)に住んでいるカッパですだよ。」
「拝島のカッパだと? それがなんでこんなとこにいるんだ。 正直にわけをいわねえと、ぶっ殺しちまうぞ。」
「へ、へぇ、それだけはごかんべんを・・・・・。 じつは・・・・・。」
カッパは、ブルぶる ふるえながら話しだした。 それによると、青梅の権左淵には、魚がたくさんいて、それがまたかくべつうまいといううわさが伝わってきた。 それでカッパは、権左淵へ魚を食いにきていたのだった。 きのう、あんまりあたたかくていい気持ちだったので、水の中でひるねをしていた。
すると、目の前につかまるのにちょうどいい綱のようなものがさがってきた。 カッパは、それにつかまって、うとうと・・・・・。
「はっと気がついたら、いつのまにかこんなところへきちまってたんですだ。 ど、どうかごかんべんを!」
カッパは、水かきのついた手を合わせた。
そこへ殿様の剣術道場の先生がやってきた。
馬丁はわけを話した。
「これカッパ、二度と権左淵へきてはならぬぞ。 先日から、村の漁師が魚が捕れぬとこぼしていたのだ。 川の魚もわれらには大切なもの。 しかと約束できねば、この場で斬って捨てるぞ。」
「へへぇ。 もうけっしてしません。 命だけはお助けを。」
「だが、カッパの口約束など、あてにできぬな。 二度とこないという証拠を見せろ。」
先生にきつくいわれたカッパは、しばらく考えていたが、つと頭を上げた。
「あのう、それでは証文を書いておくことにしますだで、矢立てと紙をかしてくだせえまし。」
「なんだと? カッパが証文を書くというのか。 これはおもしろい。 これ、矢立てと紙をもってまいれ。」
馬丁は、いそいで矢立てと紙をとりに行った。 カッパは、紙をうけとると、なにやら字のようなものをすらすらと書いた。
とこらが、カッパの書いたものを見た先生は、怒りだした。
そこには、ミミズがのたくったような、なんとも奇妙な字が書いてあった。
カッパと先生のやり取りを見ていた馬丁が、おそるおそる口を出した。
「もし、先生、ちょっくらそれをおらに見せてもらえねえだんべか。」
「なに、わしが読めぬものをどうしてお前にわかるのだ。」
「それでも、ちょっと。」
しかたなく先生は、馬丁に紙を見せた。 すると馬丁はにっこり笑ってこういった。
「なんと、字を知らぬお前が、カッパの書いたものなら読めるというのか。
ワッハッハッ・・・・・。
こいつは愉快じゃ。 なるほど、そのようなこともあるかもしれん。 それでは、カッパの証文はお前につかわそう。 すきなようにいたすがよい。」
「へい、ありがとうごぜえます。」
カッパは、拝島へ帰り、馬丁は、証文を家代々の家宝にしたということである。