青梅ナビ
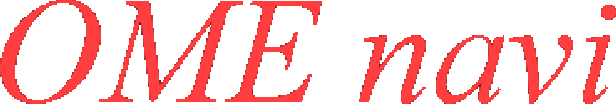
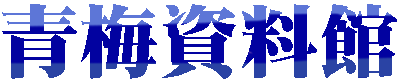
キツネ火
トミ、トミはいらんかね。」
むかし、背中に小さな箱を背負った 「トミ売り」 のおじいさんがきた。
どうだね。 トミを一つ買っておくれ。 これを買って神棚にあげておくと、銭がうんとたまるよ。」
おじさんは、そんなことをいいながら、家いえを歩いた。
あるはた屋にもやってきた。 そこのおかみさんは、このおじいさんに不吉な胸さわぎを感じた。 そこで、いいことを思いついてこういった。
「うちにわね、トミはいるからいらないよ。」
そのはた屋には、トミという名前の女中がひとりいたので、とっさにそういったのだ。
「へい、そうですか。」
おじいさんは、行ってしまった。
その夜のことである。
はた屋のうらの竹やぶには、かぜの神様というのがあって、近所の人はよくお参りにきた。 そのかぜの神さまにお参りにやってきた人が、血相をかえてはた屋にとびこんできた。
「む、むこうにキツネ火が見えるだよ!」
おかみさんが外に出てみると、むかいの山から右の方の家まで、てんてんとちょうちんのような火がつづいていた。
赤い火は、ついては消え、消えてはつき、一町(約100m)ほどもつながっている。
そんなことがあってからまもなく、キツネ火とつながった家では、景気がどんどん悪くなっていった。 その家は、トミを買ったのだそうである。
村の「キツネツキ」だといわれていた子供が、「トミっちゅうのはキツネのことだよ」と、いったそうである。