青梅ナビ

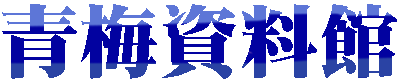
二間の岩の狼
むかし、沢井の山奥で、数人のきこりが木の伐採をしていた。 山の中に仮小屋をつくり、いく日も泊まり込んでする大仕事だった。
伐りたおした木は、りんといって山の斜面に横に積み重ねておく。
ある日、いちばん年の若い孝平さんが、伐った木にトビグチをひっかけて、山の上からおろしていると、りんの上に猫とも犬ともつかない動物が、ちょこんと乗っていた。
全身は茶色い毛でおおわれ、青光りする目でじっと孝平さんを見ている。 うすきみ悪くなった孝平さんは、思わず石をひろって投げつけた。
すると、それは、ひらりとりんから飛びおり、下にある「二間の岩」とよばれる大岩のかげに走りこんでしまった。
その夜、きこりたちは、仮小屋で休んでいた。 まん中にあるいろりをかこんで、酒を飲み、よもやま話に花がさく。
家族とはなれての山小屋暮らしは、さびしくもあるが、男同士の酒盛りは、気楽でたのしくもあった。
夜もふけて、「さて、そろそろ寝るべえ。」
と、だれかがいったとき、
ガラ、ガラ、ガッキーン!
とつぜん、ものすごい音。 ランプの灯りが、ふっと消えた。 いろりの火まで、すうっと消えていく。 と、こんどは、
仮小屋は、山の斜面からころげ落ちそうにゆれだした。
「くわばら、くわばら・・・・・。」
きこりたちは、外へ逃げだすこともできず、ふとんをかぶってふるえているばかりだった。
やっと夜があけると、さわぎはうそのようにおさまってた。 年寄りのきこりがいった。
「孝平、お前のせいだぞ。 きのうりんの上にいたけものをかまったんべ。 ありゃ、二間の岩に住んでいる狼の子だったにちげえねえ。 だから母狼が怒ったんだよ。 狼をいじめると、たたりがあるっちゅうけど、ほんとうだ。 もうけっしてかまうじゃねえぞ。」
「うん。」
孝平さんばかりでなく、ほかのきこりたちも、肝に命じたということである。