青梅ナビ

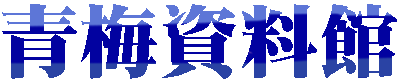
高土戸の飛助
成木の高土戸というところに、とても身の軽い男がいた。 あまり身が軽いので飛助といわれていた。
飛助は、あっというまに屋根に登り、高い木も平気のへいざだった。
「おうい、飛助、柿をもいでくれ。」
「へーい!」
「おうい、飛助、屋根にタコがひっかかった。 取ってくれ。」
「あいよ!」
「飛助、何が見える?」
「下の和尚さんが、こっちへくるぞ。」
というぐあいに、飛助は村人に重宝がられていた。 また、それだけではなく、飛助には特殊な能力がそなわっていた。
屋根にのぼって見ているわけでもないのに、
「あっ、小曽木の名主さんが、峠をのぼってくる。」
などといった。
「うそこけ、見てもいねえのに。」
「だって、おらにはわかるだもの。 うそじゃねえよ。」
そんなやりとりをして、しばらくすると、ほんとうに小曽木の名主がやってきた。
「お前ん家の今夜のめしは、大根の入ったおじやだな。」
そんなこともいった。
「においでもかいだのか?」
「いいや、ふたを取ってもみねえよ。」
「じゃ、さっき、おっ母が大根を切っているのを見たんだべ。」
「それも見ねえよ。 そんなことしなくとも、おらにゃわかるだよ。」
「よし、そんじゃ、この中に何が入ってるかあててみろ。」
村人は、飛助にかくして鍋の中にいろいろなものを入れてさしだした。
「ええと、ごぼうに、豆に、なっぱに、あ、それから芋(イモ)のしっぽも入ってらあ。」
飛助は、全部正確にあててしまった。
今でいうと、超能力少年であった。 文明の利器のなかった時代、飛助は神がかりか、魔法使いのように思われたことであろう。