青梅ナビ

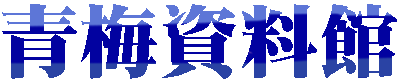
のぞき岩の天狗
夕方、仕事を終えたきこりたちは、山をおりはじめた。 のぞき岩、といわれる見あげるばかりの大岩の下を通りかかったとき、源さんという人が岩の上を指してさけんだ。
「あっ、変なものがいる! 白い着物を着た大男が、見下ろしている。」
仲間たちが、大岩を見上げたときには、もうだれの姿もなかった。
「うそべえこくなよ。 だれもいやしねえじゃねえか。」
仲間たちは、源さんの言うことを信用しようとしなかった。
「うそじゃねえ。 たしかにいただ。 おっそろしく大きな男で、顔がまっかだった。」
源さんは、いいはった。
「よし、みんなが信用しねえなら、おれがたしかめてくる。」
源さんは、大岩をのぼりはじめた。
「よせよ。 もう暗いからあぶねえぞ。」
仲間がとめるのもきかず、源さんは岸壁に足をかけてのぼって行った。
もうすこしでのぼりきれそうなところまで行ったとき、ガラ、ガラッと岩がくずれた。
「わっ!」
源さんは、岩といっしょにすべり落ちた。
「だからいったじゃねえか。 あんな高いところに、だれもいるはずはねえよ。」
「ううーん、いてて・・・・・。 いいや、いただ。 あらは、天狗さまにちげえねえ。 いてて・・・・。」
源さんは、足の骨を折る大けがをしながらも、まだそういっていた。
天狗さまを見たおかげかどうか、源さんは百歳ちかくまで丈夫で長生きだった。